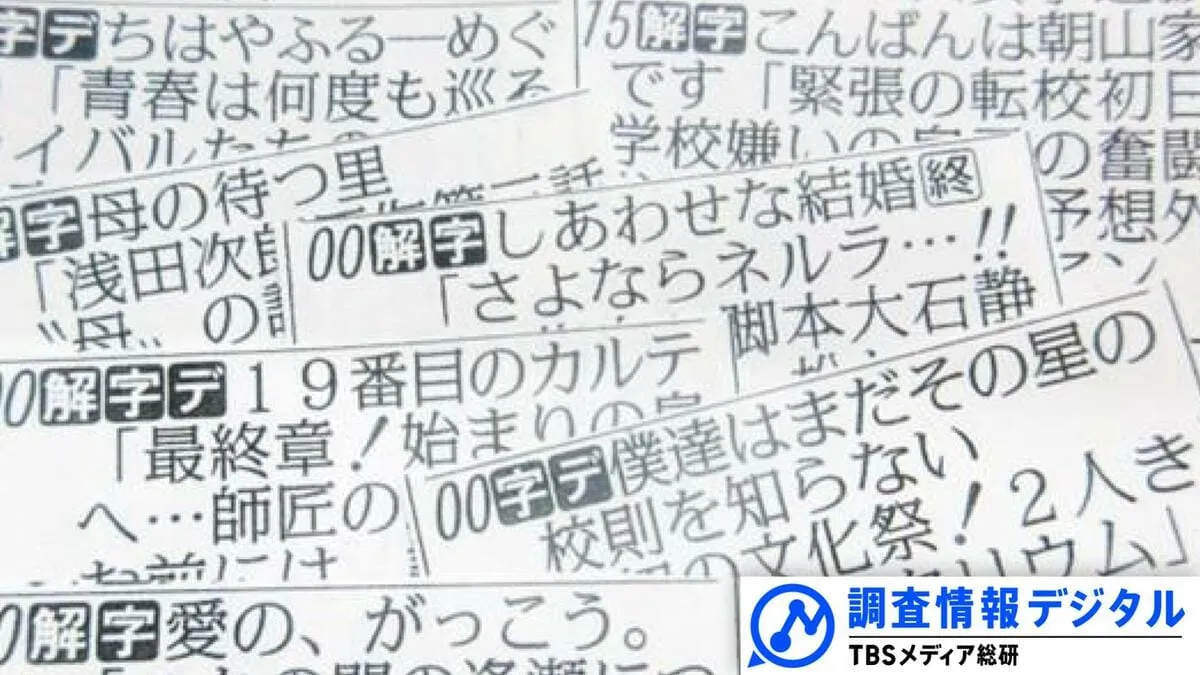
2025年7月期のドラマについて、メディア論を専門とする同志社女子大学・影山貴彦教授、ドラマに強いフリーライターの田幸和歌子氏、毎日新聞学芸部の倉田陶子芸能担当デスクの3名が熱く語る。
本当はしあわせじゃない?「しあわせな結婚」
影山 「しあわせな結婚」(テレ朝)からいきましょう。脚本の大石静さんはこの作品について「完全なホームドラマにしたかったけど、テレ朝さんはサスペンスが好きなのでサスペンスもちょっと入れました」と言っているんです。どれぐらい本音かわかりませんが、サスペンスとしてもすばらしい。
真犯人は誰なのか、家族の中にいるのかが大きな幹としてありつつ、ホームドラマとしてしっかり辛口に、時には存分に遊んでいる。ホームドラマとサスペンスをよくぞ同居させたなと思います。
特筆すべきは阿部サダヲさんです。今回は丸々二枚目路線ですよね。
田幸 そうですね。
影山 全然コメディ路線じゃない。敏腕弁護士で、テレビのコメンテーターとしても売れっ子で、しかも決しておもしろ弁護士ということでもない。むしろ三枚目的な役割は松たか子さんが担っていました。
パンのCMをやっていながら、あんなクロワッサンの食べ方をしていいのかとか、あんな寝相でいいのかとか、かなり遊んでいる部分も大石ワールドで、存分に楽しませて頂きました。
結末についてですが、ある記者が放送前に「『しあわせな結婚』ですから、最後は幸せになるんですか」と聞いたんです。そうしたら大石さんは「いやいや、『しあわせな結婚』で、そのまま幸せにはなりませんよ」と言い切りました。
でも、最終回をただ普通に見ていたら「幸せな結婚じゃないか」と思うんです。しかしよくよく見るとそうではない。見ていてまだそこに気づいていない方は、どうぞラストの数分をもう一度ご覧下さい。幸せな結婚じゃないかもしれないところが深かったと思います。
田幸 最初から「何だ、この不穏な空気は」という感じでした。松さんが魅力的なんですけど、わけのわからない不気味さ、怖さもはらんでいて引きつけられました。
ミステリーを軸としつつのホームドラマ。大石さんの意図が正解だったと思うのは、SNSの反応を見ていると、ミステリー要素が強めになると見ている側は長いと感じるんですね。家族のかけ合いの方を見ていたいという声が多くて、それが今のドラマに求められているものなのかと感じました。
謎解きは、真ん中を貫いているようでいながらメインじゃない。あくまで家族とか、人が人を思う気持ちをメインにしているのが、うまいバランスでした。
影山 確かにそうですね。
田幸 「ライオンの隠れ家」(2024・TBS)も、もともと考えていたものにミステリー要素を加えた方がいいと言われて、ああなったとプロデューサーが言っていました。ここのバランスは難しいです。ミステリーに走る方が楽なところもあるので、「ライオンの隠れ家」と同じく、そこを見失わずにちゃんと人間ドラマを貫いたのが「しあわせな結婚」のうまさでした。
「解決しない」のがすばらしい「僕達はまだその星の校則を知らない」
田幸 「僕達はまだその星の校則を知らない」(フジ)の主人公はスクールロイヤー(学校におけるトラブル等を法的に解決する弁護士)で、非常に現代的なテーマでした。取り上げる問題も、制服のジェンダー問題、いじめ、スマホによる盗撮と、まさに現在起こっている学校の中の問題を全部取り上げるぐらいの意欲作でした。
いろんな問題を取り上げつつ、どれも話題性狙いになっていない。問題が非常にリアルで、簡単に解決しないところもそのまま見せている。もともと男子校と女子校の統合によって起こってしまった問題がたくさんあって、わかり合えない人たちが、わかり合うための一歩を踏み出す。解決はしないけれど考えるきっかけにはなる、その導きが本当に丁寧でした。
今、学園物が一つのトレンドになっていると感じますが、昔みたいにワイワイ楽しいというものではありません。「御上先生」(2025・TBS)でも取り上げてきた「個人の問題は社会の問題」、これがこの作品でも描かれているんです。
社会のシステムがもう限界なのに、それをそのままにしてしまっていることを、学校をとっくの昔に卒業している私たち大人も考えさせられる。そしてつくり手は、今の学生の置かれた複雑で大変な状況に対して、とても温かいまなざしを投げかけている。それが魅力でした。
同時に「大人が悪い」のではなくて、大人にだってケアが必要だと伝えている。大人ならいろんなことがわかっていて、いろんなことができるわけじゃない。大人もみんな悩んでいるんだという、隅々にまで目の行き届いた優しい物語でした。
倉田 優しい物語と厳しい現実のバランスがうまくとれていました。優しいだけだとつくり物感が出てしまうし、厳しい現実だけ突きつけられると見続けるのがしんどい。つくり手の意識がすごく高いと感じました。
個人的に楽しみだったのが、磯村勇斗さん演じる白鳥弁護士が発するオノマトペ。「ムムス」とか。脚本の大森美香さんの造語だそうですが、白鳥弁護士という独特な感性を持った人物を表現する上で、やはりこの人何か違うなと、オノマトペだけで伝わる。大森さんの言葉に対するセンスを感じました。
影山 主人公の人物造形がいいですね。磯村君の内省的な描写がすばらしい。目をみはるものがありました。
僕の世代にとっての青春ドラマは、村野武範さんの「飛び出せ!青春」(1972・日テレ)とか、中村雅俊さんの「われら青春!」(1974・日テレ)で、非常にシンプルです。グレているといっても、正味50分の中で解決して最後は窓から飛び出して海へ行く。そういうのどかな時代を経て、様々な問題を抱えている難しい時代にフィットした、ふさわしい青春ドラマになったと思います。かつての青春ドラマをディスるつもりはなくて、自分にとっては本当に宝物ですが、50分の中で「解決しない」すばらしさですね。
それから、人の数だけ正義があるというか、立場が変われば何が正しくて何が間違っているかも変わる。だから、法律で裁けることはごくわずかなんだということも見せてくれました。
もっと見たかった「19番目のカルテ」
田幸 「19番目のカルテ」(TBS)が印象に残りました。総合診療科という題材のピックアップがいい。私の高校時代の友人にまさに総合診療科医がいます。総合診療科という言葉を初めて聞いたのは彼女が医師になった二十数年前で、そんな科があるんだと感心したんですが、浸透するまで意外と時間がかかったなと思います。
総合診療科の仕事のあり方をしっかり描いたところもよかったですし、病院の経営難も描かれていて、今医療物をやるときに経営問題はスルーできないと痛感しました。現実の医療にはお金を含めて問題が山積しているので、このドラマがこの題材を今描くことに意義があったと思います。松本潤さん演じる主人公も魅力的だった一方で、短かった…
影山 8話ですね。
田幸 もっとじっくり見たい題材でした。
倉田 私は、総合診療科について詳しくは知らなかったので、19番目の診療科として、そういうものがあるんだというところから始まりました。
おなかが痛いから内科に、けがをしたから外科にというのは誰でもわかりますが、仲里依紗さんが演じた患者さんは、全身に痛みがあるのに、どこの病院、どの診療科に行っても原因がわからない。こんなにつらくて絶望的な状況はないですよね。そういったときに窓口になってくれる「総合診療科」がある、それだけでも希望になると感じました。
あと、松本さんの師匠役の田中泯さん。もともとダンサーですが存在感が際立っていました。私は田中さんが好きなのでうれしかったです。
影山 偶然ですが、僕も甥が総合診療科医です。二十数年前、彼から「総合診療科に行こうと思うんです」と言われたので「何やそれ」と返したら「いろんな科がフォローし切れない部分を拾うんだよ」と言われて「それはおもしろい」と言った覚えがあります。
僕がコラムに、医療ドラマをやるときに病院経営の難しさを忘れてはいけないと書いたら、この作品の脚本の坪田文さんから「私も医療の現実に注目しているので、取り上げてくれてうれしかったです」という言葉を頂きました。坪田さんはその辺もよくわかった上で、上澄みだけではない部分も描かれたんだと思います。
本当にイライラ!「こんばんは、朝山家です。」
田幸 「こんばんは、朝山家です。」(テレ朝)での小澤征悦さんは、イラッとする小物感のある男が本当にうまいですね。ずっと小澤さんにイライラしながら見ていました。そして、自閉スペクトラム症の息子を演じた嶋田鉄太君のうまさが抜群でした。
影山 そうでしたね。
田幸 呉美保監督、吉沢亮さん主演の映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」(2024)にもちょっと出ていて、この子すごいなと思っていたら、同じ呉監督の「ふつうの子ども」(2025)では主演を見事につとめました。今後さらに引っ張りだこになるんじゃないかな。恐ろしい役者だと思います。
影山 びっくりしましたね。
田幸 びっくりしました、本当に。
倉田 小澤さん演じる夫には、私もちゃんとイライラしました。承認欲求が強いくせにみみっちい。そして中村アンさん演じる奥さんも終始イライラしている。まあ、こんな夫がいたら、これだけイライラしてもしょうがないと共感しました。
でも奥さんは、夫の(脚本家としての)才能を信じているからこそ、イラつきながらも応援しているわけで、夫婦、家族として信頼し合っている背景が伝わってくる。結局、素敵な夫婦じゃないかと感じたりして最後まで楽しく見ました。
影山 松尾諭さん演じる親友が泣くところはドスンときました。あのメッセージはすごく響きました。作者は似たような経験をしているんじゃないか、そんな気にさせるぐらいリアリティのある場面でした。
「引っ張る力」が強かった「愛の、がっこう」
田幸 「愛の、がっこう。」(フジ)がよかったです。女性教師とホストの恋愛で、ホストの世界を描くというので最初は警戒して見た方もいたと思うんですが、盛り上がりという意味では今期一番でした。井上由美子さんは大ベテランだけあって、次を見たくなる描き方が上手です。
ラウールさん演じるホストは学校に行きたかったけど行けなかった人。いわゆる毒親で、彼にディスレクシア(識字障害)があることに親も学校も気づかないままで、自分の名前も満足に書けない。でもコミュニケーションは上手で、人の気持ちに寄り添える。
一方の木村文乃さん演じる教師は、過干渉の親に閉じ込められ、コントロールされて生きてきた。だから恋愛の仕方を知らなくて、恋人をストーカーしてしまったあげく死ねと言われて海に飛び込んで、勤めていた出版社を辞めて教師になった。
それぞれに欠けた者同士が出会い、木村さんはラウールさんに文字を教える。ラウールさんは、ずっとばかだと言われてきたけど、本当はばかじゃないんだと初めて言ってくれた先生を好きになる。先生は先生で、ずっと親のコントロール下にいたけれど、彼との交流で人の気持ちを考えるようになり、学校で無視されていた生徒たちともコミュニケーションがとれるようになっていくという、どちらも成長物語として描かれています。
社会の問題を描きつつも筋立てがすごく強いので、韓国ドラマにあって今の日本のドラマになくなっている「引っ張る力」がありました。尻上がりにどんどん盛り上がって、最終的にはすごくバズったドラマになりましたね。
そしてラウールさんの、ともすれば悪目立ちしかねない危うい華があるところを、木村さんが上手にバランスをとっていて、木村さんってこんなに上手な方だったんだと改めて思いました。
倉田 初めは女性教師とホストという組み合わせはどうかなと思いながら見始めたんですが、どんどん引き込まれました。
私は職業にとらわれてしまっているんだと思いました。どんな職業同士で恋愛してもいいのに、女性教師とホストの恋愛イコール禁断という自分の思い込みに気づかせてくれた面もありました。
木村さん演じる教師は結局学校を辞める形になって、生徒にさようならも言えずに一旦は去ります。しかしその後、教室ではなく体育館で最後に生徒たちに会うシーンがあるんです。その場で生徒たちが木村さんにどんどん文句をぶつけるんですね。気持ちとしては学校を辞めてほしくない、でも文句をぶつけるというシーンに感動して、泣きそうになりました。
影山 僕が注目していたのは、木村さんの父親役の酒向芳さんです。あのキャラはすばらしい。酒向さんが出てくるとワクワクする、そういう存在でした。
「ちはやふる」と「スティンガース」
倉田 「ちはやふる-めぐり-」(日テレ)ですが、かるたに限らず、青春時代に仲間と一緒に一つのことに情熱を傾ける、それってやっぱりいいなと感じました。年をとってもまだそこに感動できた自分がちょっとうれしかったです。
田幸 私はもともと原作が好きで楽しんで見ました。映画版(2016・18)の10年後を描いているんですが、原作者がプロットから参加しているからこその、原作ファンも文句の言いようがない出来栄えでした。
あと、映画の「ちはやふる」は、広瀬すずさん演じる千早ちゃんという、割とがさつで残念だけど圧倒的なヒロイン、もう本当に主人公にしかならないような女の子が主人公で、気持ちのいい物語でしたが、今回描いたのは主人公じゃない側の人たちでした。
圧倒的ヒロインタイプの原菜乃華さんに対して、コンプレックスを抱いている當真あみさんをメインに置いた、そこが非常に今どきの設定でした。大体の人は主人公になれない側なので、今回の設定に共感する方が多いんじゃないかと思います。
さらに物語をつなぐ存在として、上白石萌音さんが先生役で出ています。教養も品もあって、言葉を大切にする人が過去と今をつなぐという形も見やすくて、上白石さんの存在感もすごいなと改めて思いました。
影山 上白石萌音、よかったですね。
田幸 彼女は声もいいですよね。
影山 森川葵さん主演の「スティンガース」(フジ)が気に入って、次週が楽しみでした。森川さんは器用な人で、笑いのセンスもあってお芝居もうまい。その彼女がおとり捜査専門で事件を解決していく物語です。
最後の3話は結構シリアスですが、ベースはお笑いというか、わかりやすく言えば「ルパン三世」チックなユーモアがある。脚本は「おっさんずラブ」(2016~24・テレ朝)の徳尾浩司さんで、緊張感があるけれども楽しんで見られる、その辺のバランスがうまかったのでもっと話題になってもよかったと思います。
田幸 森川さんはいろんなチャレンジをどんどん成功させている、おもしろい方ですね。
テレ東らしさがでた「私があなたといる理由」
田幸 「私があなたといる理由」(テレ東)を評価したいです。
20代のカップル、30代の夫婦、熟年夫婦という3組が、1週間のグアム旅行に行く。テレ東はもともと制限や条件をいっぱいつけて、ミニマムにつくればつくるほど、らしさが出てきます。この作品でも、恋人、夫婦というミニマムな関係性で1週間限定、さらにグアムという島が舞台という設定が秀逸です。
その1週間でふだん言えないことを言おうとする人もいれば、自分たちの関係を見直したいと思っている人もいる。他のカップルとの交流もあって自分自身を見つめ直す機会を持つ。
旅行に行くと、思いがけない本音、本性が見えて、友人や恋人関係が気まずくなることが現実でもありますが、限られた非日常の中で自分と相手に向き合わざるを得なくなる。意外と深い人間ドラマでした。
倉田 ただ、海外旅行先で離婚の話は重い(笑)。せっかく楽しみに行ったのにと思いつつ、言い出した方としては、普段の生活の中では言えないことを非日常な場所だからこそ言える、そういう心理をよく捉えていると思いました。
20代のカップルは妊娠していて、逆に30代の夫婦は子どもをつくろうか悩んでいる。そういうセンシティブな話も、日常と離れた場所だからこそ突っ込んでできる。そこが伝えたいことなんじゃないかと感じました。
意外な展開だった「母の待つ里」
倉田 「母の待つ里」(NHK)が刺さりました。浅田次郎さんの原作も読まず、事前情報も入れずに、中井貴一さん演じる会社の社長が田舎のお母さんに会いに行くストーリーだと思って見始めたんです。
一昔前のステレオタイプな田舎が舞台だなと感じながらも、なんか変な違和感がある。何よりもまず、宮本信子さん演じる母親の名前を中井さんがわからないのはなぜなんだろうとか。
ひょっとしてミステリードラマなのかと思いながら見ていくと、実は宮本さんは本当のお母さんではなく、訪ねた田舎も本当の自分の故郷ではない。「親元に帰省する」というカード会社のとても高価なサービスプランでの疑似体験だということが分かる。
中井さんや松嶋菜々子さんが、子どもとして宮本さんと疑似親子を演じていて、嘘の関係なんだけど本当の親子にすらないような心の交流が生まれるところに感動しました。
実の親子だとつい厳しくなって、親にきついことを言ってしまったりします。言いたいことを言えるのはある意味いい親子関係かもしれませんが、実の親子じゃないのに実の親子らしいものが生まれることもあるんだという気づきを与えてくれた作品でした。
ロケの場所は岩手県ですよね。美しい風景がちゃんと残っている。そういう風景を守っていきたいと思いつつも、そこにはまた過疎など別の問題も出てきて、社会のいろんな問題まで考えることができました。
田幸 私も原作を読まずに見始めました。温かなふるさとを描いているようでいて違和感がずっとある。中井さんが若年性認知症の役を演じた「記憶」(2018・フジ)というドラマを見ていたこともあって「お母さんに名前を尋ねるって、もしかして…」と考えちゃったぐらい、真相がなかなかわかりませんでした。
こういうサービスっていいなと思った反面、そのサービスを考えているのがアメリカのカード会社というところが皮肉でしたね。
影山 僕はもう父も母も見送っているので、この作品を見て感じるのは、やはり「もっと優しくすればよかった」です。実の親に対しては、つい厳しく当たってしまう。そういう後悔の念が何年もさかのぼってふつふつと出てきます。
また、子ども役を中井さんと佐々木蔵之介さんの二人だけにするとマザコン男の物語になりかねないところに松嶋さんを入れている。これは原作のうまさであり、それを反映させたドラマのうまさでした。
登場する村人たちがしっかりとお芝居をすると言いながら、あちこちに穴があるというのかな、だからこそ引きつけられるということで、あえて穴をつくっているんでしょう。伊武雅刀さんが、ポンと振られたらしゃべれなくなるとか、あのシーンよかったですね。
笑えて、深く考えさせられて、ほろっとさせる浅田ワールド。そのいいところをしっかり生かした勝利だと思います。
文化の違いを丁寧に描いた「ベトナムのひびき」
倉田 「ベトナムのひびき」(NHK)がよかったです。私はクラシック音楽担当の記者もしていたので、クラシックを取り上げるドラマはもともと好きなんです。
長く続いた戦争の影響が残り、運営もうまくいっていないベトナムの国立オーケストラに日本人指揮者が指導に行って、楽団員といろいろトラブルがありつつも立て直しに貢献するという美しいお話です。
楽団ができたのが1960年頃で、ベトナムの一般の方はクラシックにあまりなじみがない。そんな中でも音楽を志す若い楽団員がいるけれど、練習すらなかなかできないという現実が立ちはだかる。
楽団員は給料が安いのでアルバイトをしたり、病気の子どもの治療費を稼がなくてはならなかったり、いろいろな困難を抱えながらも、それでも音楽をやりたいって、どれだけ音楽を愛しているんだろうと、その情熱に心を打たれました。
また、指揮者と楽団員との間で心のすれ違いがあったり、そもそも日本人とベトナム人とで習慣や文化が違うところからトラブルや誤解が生まれます。
今、ベトナムを初め外国人の労働者がどんどん日本に入ってきています。コンビニなどで接する中で、やはり日本人の店員さんと対応が違うと感じることはもちろんあります。でもコンビニの店員さんとは深く話す機会がないからわからないだけで、彼らは彼らなりの習慣や文化でそうやっているんだろうなと、私の日常生活にも直結している話でもあると感じました。
クラシックファンとして、おおっと思ったのが、濱田岳さん演じる主人公のライバルの指揮者を反田恭平さんというピアニストが演じているんです。反田さんは2021年のショパン国際ピアノコンクールで日本人最高位の2位になられた方ですけれど、えっ、反田さんが演技してる!と釘づけになりました。
音楽をやるためには平和が必要なんだと感じたのが一番ですけれど、私たちもコロナ禍で、エンターテインメントを楽しめない時期がありましたよね。そういう経験をしたからこそ、日常で好きなエンタメを楽しめることの重要性が理解できましたし、好きなものを楽しめる世の中であり続けてほしいと感じました。
田幸 ベトナムと日本の文化の違い、そして交流が丁寧に描かれていました。今、世の中が排外主義に動いているところがあって、危ないなと個人的に思っています。外国の人が怖かったりする人もいると思うんですが、それは知らないからこそなので、海外の文化や風土を知る機会になる作品、「東京サラダボウル」(2025・NHK)がまさにそうでしたが、こういう作品をどんどん作ってほしいと思います。
「八月の声を運ぶ男」「あんぱん」が伝えた「戦争」
影山 これも語らなきゃいけないのは「八月の声を運ぶ男」(NHK)です。
倉田 被爆者の声を拾っている方がいらっしゃったということに驚きましたし、被爆体験を語れる方がどんどん亡くなっている中でこういう作品がつくられたことに意味があると思います。
いきなり「あなたの被爆体験を聞かせて下さい」と言われても、すぐには語れない方の心境も考えさせられました。被爆して10年、20年では語れなかったけれど、60年、70年、80年たってようやく語れるようになるというのもそうだろうなと感じます。
田幸 被爆されて「徹子の部屋」にも出演された森田富美子さんという方を何度か取材しているんですが、やはりご自身の話は90歳ぐらいになってようやく語れるようになったとおっしゃっていました。それまでは取材中、戦争の話になると止まっちゃうんです。「もうこれ以上、話しません」としっかり言われる。それぐらい当事者にとって語るのは大変なことなんだと思います。
影山 「あんぱん」(NHK)も戦争をしっかり描いています。しかも、日本人は被害者であると同時に加害者だということをきちんと伝えて、これは特筆すべき点です。
倉田 主人公の幼なじみが中国の子どもに殺される場面があるんですが、その子どもは日本兵に両親を殺されていて復讐のためなんです。実際に日本兵が中国で人を殺していた史実をちゃんと描いている。
「自虐史観」とよく言われますが、自虐ではなく事実は事実として日本がやった負の側面も受けとめないと、そうならないためにどうすればいいか考えることもできない。史実をちゃんと受けとめることが大事だということを、朝ドラという日本人にとって身近な媒体で描いたのはすばらしいと思います。
田幸 重要なのは、当時としては主流だったはずの軍国主義に加担した側を主人公に置いたところで、これまでの作品と大きく違う画期的なことだと思います。
朝ドラのつくり手の中では「戦争など暗いターンが続くと視聴率が下がる」と、ジンクスのように言われてきたという話を聞いたことがあります。でも「あんぱん」は、戦争の気配から後まで全部合わせると10週じゃおさまらない。さらに最終週までずっと戦争のにおいがあります。こんなに長い尺を使って戦争を描いた朝ドラはこれまでなく、そこがすばらしいです。
最終週で、アンパンマンのライバルのばいきんまんが登場します。実は、ばいきんまんの存在は重要で、アンパンマンはばいきんまんを倒すけど命は奪わない、これが大事だとやなせたかしさんもおっしゃっています。完全に倒しちゃだめだと。
体の中にはいい菌も悪い菌もいて、それが戦っているのが健全な状態。社会も同じで、完全に排除してはだめだと。みんなが同じ方向を向いてしまったら社会が危うい状態になると、やなせさんもずっとおっしゃっていて、その象徴がばいきんまん。最終週にそういう重要なメッセージもあって、朝ドラという多くの人が見る枠でこれをやった意義を改めて感じました。
最後にもう一本、「照子と瑠衣」(NHK BS)。これは映画「テルマ&ルイーズ」(1991)をモチーフにした作品ですけど、70代女性を主人公にしたのはこれまでの連ドラになかった試みです。
プロデューサーにお話を伺ったところ、ドラマでの高齢女性は「おばあちゃん枠」という役割で登場することがほとんどなので、その流れに抗して70代女性を主人公に据えたとのこと。しかも、プロデューサーのお二人も定年退職したばかりの60歳で、いろんな希望を感じさせる作品でした。
高齢の方を「おばあちゃん」「おじいちゃん」という記号ではなく、これからも人生が続いていく一人の人間として描く作品が今後たくさんつくられるといいなと思います。
影山 60代、頑張らなきゃいけませんね。励まされました。
(了)
<この座談会は2025年10月3日に行われたものです>
<座談会参加者>
影山 貴彦(かげやま・たかひこ)
同志社女子大学メディア創造学科教授 コラムニスト。
毎日放送(MBS)プロデューサーを経て現職。
朝日放送ラジオ番組審議会委員長。
日本笑い学会理事、ギャラクシー賞テレビ部門委員。
著書に「テレビドラマでわかる平成社会風俗史」、「テレビのゆくえ」など。
田幸 和歌子(たこう・わかこ)
1973年、長野県生まれ。出版社、広告制作会社勤務を経て、フリーランスのライターに。役者など著名人インタビューを雑誌、web媒体で行うほか、『日経XWoman ARIA』での連載ほか、テレビ関連のコラムを執筆。著書に『大切なことはみんな朝ドラが教えてくれた』(太田出版)、『脚本家・野木亜紀子の時代』(共著/blueprint)など。
倉田 陶子(くらた・とうこ)
2005年、毎日新聞入社。千葉支局、成田支局、東京本社政治部、生活報道部を経て、大阪本社学芸部で放送・映画・音楽を担当。2023年5月から東京本社デジタル編集本部デジタル編成グループ副部長。2024年4月から学芸部芸能担当デスクを務める。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。
・【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから?」記者と小川晶市長の一問一答(9月24日夜)
・見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証”
・「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏(28)】

