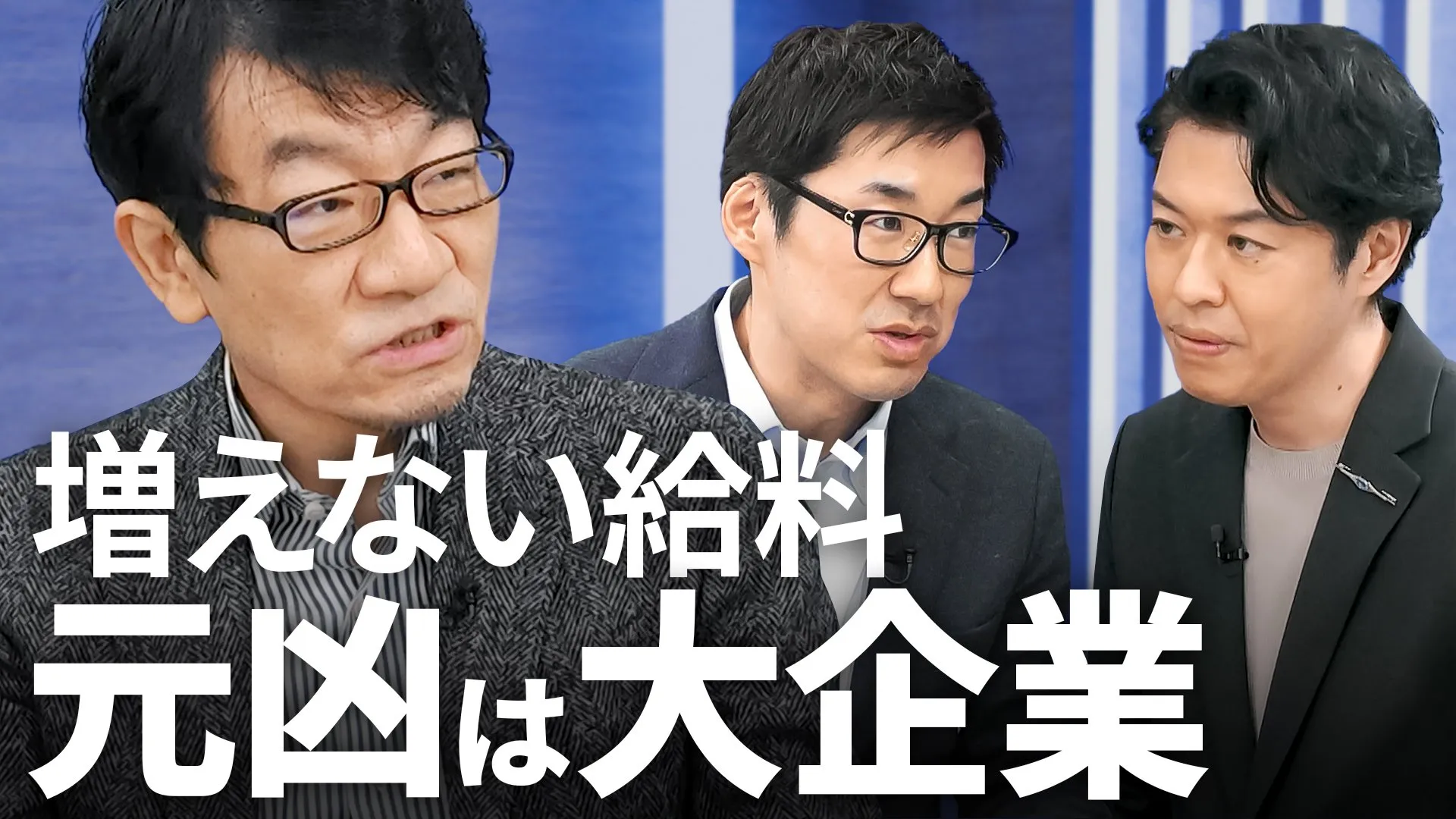
きょう25日が給料日という会社も多いと思いますが、最近は「歴史的な賃上げ」というフレーズを耳にする機会も増えました。一方で、給料が上がったという実感を持つ機会は少ないです。
【データを見る】日本の実質賃金と生産性の推移 欧米との比較も
なぜ給料が上がったと感じられないのか?
BNPパリバ証券・チーフエコノミストの河野龍太郎氏は「儲かってもため込んで、実質賃金も上げない、人的投資もしない大企業にある」と指摘。みずほ銀行・チーフマーケット・エコノミストの唐鎌大輔氏と共に解説します。
よく言われる「生産性」が原因ではない
河野氏は、エコノミストの多くが指摘する「アメリカ並みに“生産性”を上げれば良い」という点に疑問を投げかけます。
「日本では1998年から2023年までの25年間に、累計で生産性が約3割、上昇していますが、実質賃金はほぼ“横ばい”となっています。つまり(給料が上がらないのは)生産性の問題ではない」
日本の「生産性が3割アップ」という数字は、欧米と比べても決して低いものではありません。比較してみるとアメリカには及ばないものの、フランスやドイツを上回っています。
しかし、「実質賃金」は日本がアメリカ、フランス、ドイツと比べて、ずば抜けて低いという結果になっています。一体、その理由は何故なのでしょうか?
利益剰余金は約600兆円 原因は「ため込む大企業」
BNPパリバ証券の河野氏は、日本の実質賃金が上がらない原因は「儲かってもため込んで、実質賃金も上げない、人的投資もしない大企業にある」と指摘します。
実際、日本企業の利益剰余金は1998年ごろは約120兆円でしたが、アベノミクスなどを経て、2023年度には約600兆円まで膨らみました。
しかし、利益剰余金が急激に積みあがる一方で、人件費の増加は極めて小さいものに留まっています。
みずほ銀行の唐鎌氏は「日本の企業業績について話す際に、儲かっているにも関わらず、人件費が上がらない、給料が上がらないと言われてきたが、実際は逆で、人件費が上がらないから儲かっているという部分もある」と解説します。
では今後、大企業はどう発想を変えていけば良いのでしょうか?
実質賃金を考える上で必要な「2つのポイント」
実質賃金が上がらない問題と向き合う上で唐鎌氏は、「労働分配率」と「交易条件」の2点を考えるべきだと言います。
具体的には①利益剰余金が積みあがっていく中で、企業の労働者に対する分配が低いという点、そして、②円安によって高額な燃料を購入するなどして、日本企業の交易条件が悪化していったという点です。
唐鎌氏はこう結びます。
「実質賃金を語る際に何でも生産性という人が多い中で、この2点がアプローチしなければいけない(日本の)課題だ」。
===
【解説】
・河野龍太郎 | BNPパリバ証券 チーフエコノミスト(日経ヴェリタス『債権・為替アナリストエコノミスト人気調査」で2024年まで11回連続首位の人気エコノミスト。著書に『日本経済の死角 ――収奪的システムを解き明かす』、『成長の臨界:「飽和資本主義」はどこへ向かうのか 』など)
・唐鎌大輔 | みずほ銀行 チーフマーケット・エコノミスト(著書に『弱い円の正体 仮面の黒字国・日本』、『「強い円」はどこへ行ったのか』など)
【聞き手】
・竹下隆一郎
・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】
・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】
・【検証】「布団の上に毛布」が暖かい説 毛布は布団の「上」か「下」か 毛布の正しい使い方【Nスタ解説】

