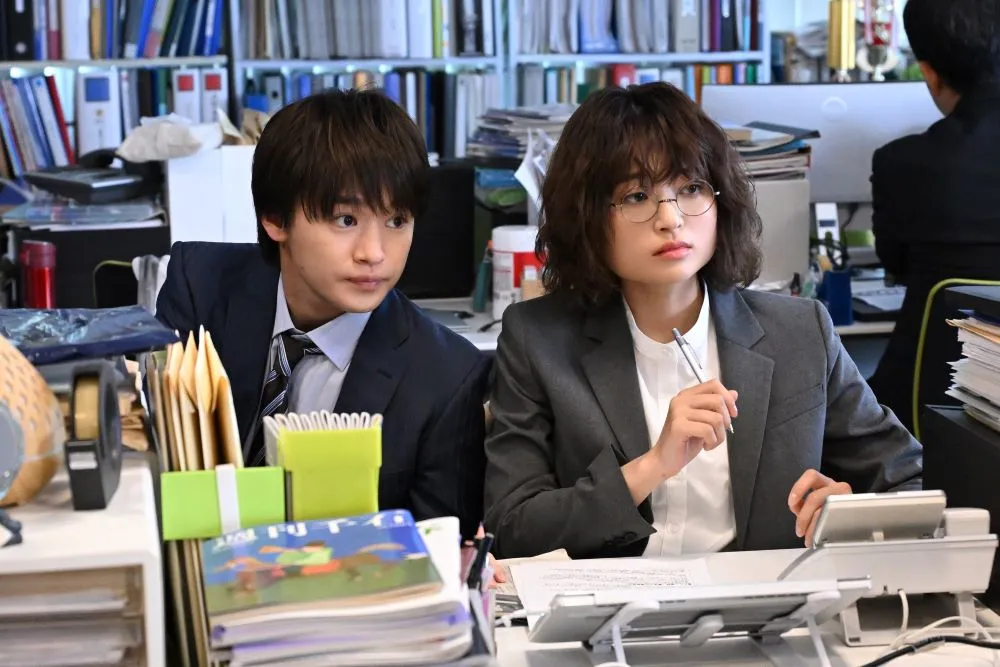
社内異動――会社員なら誰もが一度は経験し、期待やチャンスと感じる一方で、不安や戸惑いもつきまとう、時に厄介なこの制度。会社員にとって“当たり前”でありながら、その意味や目的をつかみきれていない人も多いのではないだろうか。
【写真で見る】奥山葵さんらが出演するドラマストリーム『スクープのたまご』場面写真
今回、話を聞いたのは、立教大学経営学部教授で「大人の学びを科学する」をテーマに長年研究を続けてきた中原淳さん。東京大学卒業後、国内外の大学や研究機関で学びを深め、リーダーシップ開発や組織内学習などの著書・プロジェクトも多数手がける。
話を聞いたきっかけは、現在放映中のTBSドラマストリーム『スクープのたまご』。主人公で入社2年目の信田日向子(演=奥山葵)が、思わぬ“社内異動”によって、スクープを追う週刊誌の記者となり、新たな配属先で奮闘しながらも成長していく様子を描く。
単に“命令される”配置替えではなく、自己都合の異動も増えてきている昨今。新時代の「キャリア論」も広がる中、日本の社内異動の現状はどうなっているのか。そして、それをポジティブに捉えるためのヒントとは。
研究者の視点から語られる“使えるヒント”満載のロングインタビューを、中原さんの言葉をそのままに、お届けする。
会社都合の異動は減少傾向?――日本企業「社内異動」の“今”
日本の社内異動を語る上で、まず、多くの日本企業が取っている雇用の仕方は、「メンバーシップ型雇用」というものです。メンバーとして「村」に入るようなもので、村に入ったら、村民としての「メンバーシップ」を得られます。メンバーシップを得た後はどこに配属され、異動させられるのかも、基本的には会社に任されるというのが、メンバーシップ型雇用のあり方です。
経営の目から見れば、「異動」とは、適材適所に人を配置して、人の能力を伸ばすものです。もう1つは、例えば会社としてどうしてもこの部署に誰かが必要だとなったときに、そこに人を供給するしかないので、事業を存続させるためにも必要不可欠なものです。
日本は、いったん組織に入ったら、人事権がとても強力と言われていますが、今は「自分のキャリアは自分で築いてね」というような方針を取る会社もあるので、働き手のほうがキャリアを自ら選べるように、会社都合の異動はしないという動きも出てきています。
そうした新たなキャリアのあり方が出てきたのは、今から20年ほど前で、本格化したのは、10年ぐらい前。その辺りからだんだん、「自分の仕事を自分で選んで何が悪いの?」という風潮が出てきたのではないかなと思います。
社内FA(フリーエージェント)制度と言って、社員が自らの意思で異動や転籍をできる人事のやり方もあります。
日本企業は今、とにかく人手不足で労働力が確保できないので、辞められるのが一番怖い。1番象徴的なのは、若年層は特に「転勤を嫌う」ということ。だからなるべく、社員の希望を優先して、配属先を決める傾向にあると思います。とにかく「居てもらう」ことの方が、うれしいのです。
なので、会社都合の異動が減り、自己都合の異動の割合が増えて、今は大体半々ぐらいになってきていると思います。
“ハイメンテナンス”が必要な人材とは? 社内異動の宿命と仕組み
ただし、経営を維持するためにも、会社都合の異動は今後もゼロにはならないと思います。
特に、“上澄み10%”と言われるような優秀な人材には、ハイメンテナンス(優秀な人材を引き留める維持のための投資)が必要なんです。大体入社3年目ぐらいで、ある程度の優秀な人材には目星が付けられて、将来の経営人材にもなるようなロードマップが作られているケースが多いです。
社内異動が1度に30個も40個も起きるのは、その優秀な人材1人を動かすために、“玉突き”のように発生している、ということでもあります。
僕がいつも言っているのは、20代の後半に「第1モヤモヤ期」が来て、30代の後半に「第2モヤモヤ期」が来る。「このままこの会社にいてもいいのかな」という不安が訪れるのが、第1モヤモヤ期で、第2モヤモヤ期は「この時期を逃したら、もうこの会社から出られないかもしれない」という不安から来るものです。
そして今の世代は、優秀であればあるほど、第1モヤモヤの時に辞めてしまうケースがかなり多いと思います。だから会社側も、居続けてもらえるような仕事をちゃんと渡して、フィードバックもする。手塩にかけて育てて、それに見合った人事異動もさせていくことになります。
「ジョブ型雇用」と言って、最初から社内異動がない雇用の仕方も、少しずつ広がってきてはいますが、IT企業・コンサルティングファームなど、領域は絞られていますね。
部署が変わると「違う国」――“異国”で見つける良いサプライズ
社内異動とひと言で言っても、同じ会社にいて部門が違うとなると、それはもう「違う国」なんです。価値観も、仕事の仕方も、何もかもが違います。
人は、新しい環境や状況に置かれたときに、理想と現実にギャップを感じて戸惑いを感じる、いわゆる“リアリティーショック”を受けるのですが、社内異動も同じです。
そもそも、「違う国」に入ることはやっぱり怖いので、ドキドキしますよね。結局、異動してから1年ぐらいして、そこの仕事が一回りして、「ここではこういうふうに仕事が動いているんだ」というのを把握できるまでは、怖いんです。未知のものは怖いので。
ただ、今回のドラマ(『スクープのたまご』)の話のように、実際に異動してみて、その中でやりがいを見つけたり、同僚に恵まれたりして、「違う国」に自分が定着していくこともあります。すごくリアルに描かれていると思いますね。
例えば、主人公の女性が異動前に週刊誌の仕事に対して抱いていたイメージは、もともと悪かったと思います。でも、中に入ると、自分の中で“意味づけ”の変化が起こるはずなんです。他のメディアが動けないときに「調査報道をできるのは私たちしかいない」「それが社会を変えることになるかもしれない」というふうに、良い方向に意味づけが変わるかもしれない。
だから、実際にやってみないと分からないですよね。そして、その体験は「自分で」作らなければいけない、意味を見いださなければいけないものなんです。それを「センスメイキング」とも言うのですが、最初はネガティブに捉えていたスクープを取ってくる仕事を、ポジティブなものに“上書き”するのは誰なのかと言われたら、自分しかいません。
ブラックな職場では「やりがい搾取」なども横行するので、一概には言えないのですが、大概の仕事には、やりがいや意味を見いだすことはできるんじゃないかなと思います。
【誰でもできる!】社内異動をポジティブに捉える方法
そもそも、社内異動は働き手にとっても、ネガティブな側面だけではありません。同じ仕事でも、3年ほどやっていて飽きてきた頃に、“新しい仕事”を与えられ、そこで経験から学ぶことも出てくるので、能力も伸びていきますよね。
日本でよく言われているのは、「262」の法則です。この「2・6・2」というのは、組織内の人材の比率が「意欲的に働く2割」「平均的な6割」「意欲の低い2割」に分かれるという現象を指すのですが、その平均的な6割の働き手は、実は自分のキャリアのことはあまり考えてない傾向もあります。
いったん就職できればいい、という考え方のほうがマジョリティーで、そもそも社内異動を一概にネガティブには捉えてはいないと思います。
それでも、「気が進まないな…」という異動先は誰にでもありますよね。でも、大概の人は、そこでやりがいを見つけます。適応できるんです。
“リアリティーショック”も当然受けるのですが、「思ったよりも良かった」みたいな“ポジティブサプライズ”もあります。先ほどのドラマの話もそうですよね。異動してみて、最初は嫌だと思っていても、「意外と楽しい」というような発見をしていくんです。
1番ハードな転勤や転居を伴うような異動でも、意外と適応できたりもします。例えば地方に行った場合だと、早く帰れたり、私生活が充実したりして、生活満足度にも直結します。東京は刺激もあるけれど、こっちは「きりたんぽがおいしい」みたいな発見もありますよね。
異動元の上司より、異動先の上司のほうが意外と好きだったり、人との出会いも、結局は行ってみるまでは、何が起こるか分からないとも思います。
あとは、社内異動は「何年かに何回かは起こる」など、基本的にはその会社にいれば分かってくるようになるものなので、それをあらかじめ意識しておけば、例えば現状で何か嫌なことがあっても、「ここはフルスロットルじゃなくて、流していこう」というような考え方もできます。
「30年、ずっとそこにいてください」と言われるよりも、「この場にいるのもあと何年かだ」と思えれば、異動もポジティブに捉えることができると思います。一生続くわけではないのです。また数年たてば、異動が来るのですから。
自分の「屋号」を持つ強み――現代流「キャリア志向」の“本音”
話は少し脱線してしまうかもしれませんが、今のキャリア志向は、とにかく「自分のキャリアは自分で築け」なんです。大学などでも、散々そう教育されています。
今は、自分の「屋号」をどう持つか、と考える人が増えていると思います。例えば、“物書き屋”でも“経理屋”でも、“人事屋”でも、「自分は○○屋です」と言える屋号を、30歳ぐらいまでの間に1個持っていればいい、と思っているキャリア志向の人がすごく多いと思います。
その屋号を持っていれば、社内異動どころか、どこの会社でも通用するという考え方ですよね。転職するにしても、屋号を持っていれば、そのカードをいつ切るのかは自由なので、会社にいる間は、社内異動でいろいろと経験を積むという考え方もあります。
これからの時代は特に、「何をしてきたか」「何ができるか」という実績を積み上げて、より解像度の高い話ができるようになることが、キャリアを築く上で重要なことだと思います。
・【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから?」記者と小川晶市長の一問一答(9月24日夜)
・見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証”
・「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏(28)】

