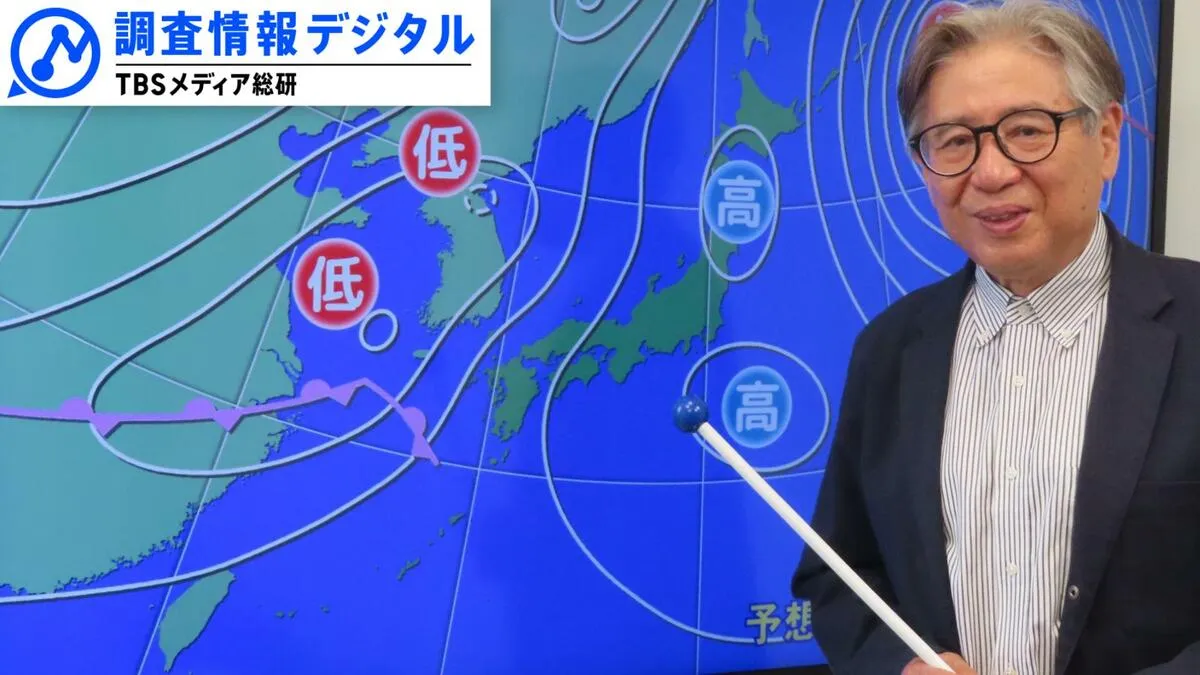
2025年夏の日本の平均気温はこれまでの記録を大幅に上回り、統計開始以降で最も高くなった。気象予報士の森田正光氏に、異常な気象について分析してもらうとともに、今伝えるべき気象情報などについて聞いた。
【写真を見る】猛暑日を記録した地点が3年で1.5倍以上に!もはや「異常気象」ではなく「気候変動」~森田正光気象予報士が今伝えたいこと~【調査情報デジタル】
異常気象が常態化して「気候変動」に
――2025年夏は記録的な高温でした。気象庁は6月から8月の平均気温の基準値からの偏差が+2.36になったと9月1日に発表しました。これまでの記録だった2023年と2024年の+1.76を大幅に上回り、1898年の統計開始以来最も高い記録です。この異常な高温をどうとらえていますか。
森田 国内で猛暑日になった地点の数は、暑い年だと言われた2010年や2013年でも4000前後でした。ところが今年は約9500もありました。これは過去最多です。一昨年は6000弱、昨年は9000弱だったので、この3年で猛暑日の地点数が1.5倍以上になるというとんでもないことが起きているんです。
――毎年のように異常気象と言われていますが。
森田 気象庁は「30年に1回くらいの頻度で起こること」を異常気象と定義しています。30年に1回の高温が3年も続くと、もはや異常気象ではないですよね。異常気象が常態化している今の状態は、気候変動と言い変えられます。今、人類は気候変動を経験しているのです。世界的に温度が最も高かったと考えられている平安時代から鎌倉時代の頃以上に、今は温度が高くなっています。
――なぜ平安時代から鎌倉時代の気温が高かったことが分かるのでしょうか。
森田 気象を類推する方法で、世界的に有名なのが福井県年縞博物館による調査です。三方五湖の一つである水月湖は、川につながっていないため、底にいろいろなものが積もっています。ボーリング調査で、その7万年分の堆積物を調べることで気温の変化が分かり、平安時代から鎌倉時代が最も高いことが判明しました。
『徒然草』に「家のつくりやうは、夏をむねとすべし」という有名な一節があります。これは、夏は暑くてどうしようもないから、夏のことを考えて家を作ろうという意味です。暑さに対応するために寝殿造や、庭に川や滝を作る文化が残りました。
――高温の原因は分かっているのですか。
森田 複数あるうち有力な説が、ミランコビッチ・サイクルです。コマが回転するとき、コマが微妙に首を振りますよね。自転している地球にも同じ現象が起きることで、太陽の当たり方が変わります。このサイクルによって気候が変わることが知られていて、当時は太陽の放射量が増えていました。しかし今はそういうサイクルでもないのに温度が上がっているんです。
――8月5日には群馬県伊勢崎市で、国内歴代最高の41.8度を観測しました。
森田 かつて40度以上の気温は、1933年に山形市で観測された40.8度が最高でした。これはフェーン現象によるものです。それが2007年に記録が破られると、40度以上が頻繁に出るようになります。今年の夏も多くの地点で40度以上が観測されましたし、北日本、東日本、西日本の平均気温が、平年より低くなった日はほとんどありません。「温暖化はしていない」と議論する人たちが今でもいますが、データを見れば温暖化していることは誰も否定できないでしょう。
――温暖化は人為的な問題ではないと主張する人たちもいます。
森田 今の温暖化は人間の関与がないと起こり得ないと言われています。最近はイベント・アトリビューションという考え方があって、人間の活動がどれくらい気候を変えているのか、大雨が降った場合にはどれだけ人間が関与しているのかなどを、科学的手法で評価できます。この手法によって、最近は人間の活動が8%から10%、気候に影響しているのではないかと見られています。そういう意味では、人間が関与した気候変動が起こり始めていると言っていいと思いますね。
温暖化による生命の危険と生態系の変化
――温暖化は私たちにどれだけ深刻な影響を及ぼすのでしょうか。
森田 生命への深刻な影響でいうと、熱中症が挙げられます。ただ、熱中症以外にも、熱関連死と呼ばれる暑さに関係して引き起こされる死や、事故も増えているようです。
――地球全体では、どのような影響が考えられますか。
森田 一切食料が育たなかったシベリアで小麦がとれるようになるなど、温暖化によって得になることもあります。冬が暖かくなるのでいいじゃないかという考えももちろんあるでしょう。けれども、温暖化の「損得」の研究も進んでいて、現在では温暖化は地球全体で損になると考えられています。
――温暖化で良くないのはどんなことでしょうか。
森田 南にあるものは北に、北にあるものはどんどん追いやられて、とれなくなるものが出てくることです。今年は東北で伊勢エビがとれたことが話題になりました。バナナは今まで北緯28度まででしか生育できないとされていたのが、29度、30度へと生育地が北へ上がっています。ミカンやリンゴの生産地も北に移動しています。
その一方、それまで育っていた地域でミカンやリンゴは滅びてしまいます。稲は北海道で作付面積が広がりましたが、西日本では高温による熱障害が起きていますよね。さらに、人間が管理できるものはまだいいけれども、実は人間が管理できずに滅んでいくものがたくさんあります。
――例えばどのようなものですか。
森田 木などの植物です。植物は最も適した温度帯で生育範囲を広げていきます。平均気温20度のところで育っていた木は25度になると滅ぶので、北上が始まります。けれども、温暖化のスピードがゆっくりであれば移動できますが、急に温度が上がると植物は対応できません。
さらに、地球上には500万から3000万種類の生物がいると言われていますが、そのほとんどは微生物です。微生物は植物に依存していて、植物が枯れると滅び、その微生物に依存している昆虫も滅びます。昆虫が滅ぶと鳥も食べるものがなくなります。人間は食物連鎖の最上位にいるので気付かないけれど、ある日いろいろなものがなくなるかもしれないのに、大丈夫だといってチキンレースをしているのが今の状況ではないでしょうか。
――植物や昆虫は、日本でも減っているのでしょうか。
森田 僕は日本生態系協会の理事をしていて、確実に減っていると報告を受けています。虫も減っていて、都会で蚊に刺されることはなくなりました。もちろん、都市は便利だし、蚊がいないことはありがたいので、ある程度はしようがないと思っています。ただ、都会とその周辺でバランスをとって、虫が生息できるところをとっておきたいですよね。
――都会で小さな緑地を作ることにも意味があるのでしょうか。
森田 赤坂のTBSの敷地には、小さなビオトープ(注)があります。あんな小さな場所に意味があるのかと思う人もいるかもしれませんが、あそこにはタマムシが皇居から飛んできます。死骸を何度か見つけたことがありますよ。小さな空間でも1平方キロメートルの中にいくつか作ると中継地になって、虫にとってはありがたいわけです。
もっと言うと、明治神宮は人口の林です。明治天皇が亡くなったとき、あの場所は湿地帯でした。そこに伊勢神宮のような立派な神社を作ろうとして、スギやヒノキを植える案があったのです。しかし植物学者の本多静六が、近くを蒸気機関車も走っているのでスギやヒノキでは駄目になってしまうと反対して、日本中から木を集めて森を作り、さらに森の中に人間が手を加えない領域を作ることを提案しました。
(注)「生物の生息空間」を意味するが、特に人工的につくられたものを指す場合が多い。
――人工林によって生態系を成立させているのですね。
森田 昔の林がそのまま残っていると思っていたら大間違いです。都会の中にもビオトープのようなものを作ることで、生物にとっては全く違う世界が生まれます。環境を守るといっても、もともとある自然を残すだけでなく、多角的に考えた方がいいと思いますね。
飛躍的に精度が上がった気象予測
――森田さんは日本気象協会に入職して1974年から東京本部で活動し、1992年に日本初のフリーランスのお天気キャスターになり、民間の気象会社であるウェザーマップを設立されました。半世紀以上気象情報に携わってきて、どのような変化を感じていますか。
森田 コンピューターによる予測の精度が良くなったことですね。東京に転勤した頃はコンピューターによる数値予報と言われるデータがあったものの「こんなものは当たらないだろう」と参考にする程度でした。それが、1977年に気象衛星ひまわり1号が打ち上げられたのを境に、どんどんコンピューターの予測が良くなりました。
僕にとっての分かれ目は、1990年11月30日に紀伊半島に上陸した台風28号でした。日本で最も遅く上陸した記録を持つ台風ですね。3日前くらいに数値予報が上陸するデータを出しているのを見て、みんなで「ありえない」と笑っていました。10月でも5年に1回くらいしか上陸しないわけですから。ところが、本当に上陸しました。この結果を受け入れて、それからはコンピューターと人間とが違っていたら、コンピューターを信じるようになりました。
――その4年後の1994年からは、気象予報士制度が始まりましたね。
森田 一回目の試験で不合格だったのは、今でも心の傷になっています(笑)。制度ができたのも、コンピューターの精度がすごく良くなって、ガイダンスを読み取ることで予報ができるようになったからです。それまで内輪では、気象予報には「屋上派」と「地下室派」があると言われていました。屋上派は外に出て、今の天気を見ながら今後の予報を語る人。地下室派は空を見ずにコンピューターと数字だけで考える人です。
――ということは、森田さんは地下室派ですか?
森田 もともと屋上派でしたが、1990年の台風28号をきっかけに心の中では地下室派に転向しました。でも、視聴者の皆さんは天気を見ながら伝えてほしいと思うでしょうから、数値予報を使って予測しながら、外に出て伝えていました。だから、僕の予報は当たるんじゃないかといった信頼を得ることができたと思います。
気象予報士はもっと自分の考えを発信してほしい
――気候変動と表現された今の異常な気象を伝える上で、もどかしさを感じることなどはありますか。
森田 気象予報士制度ができてから、天気の伝え方が防災一辺倒になっています。お天気キャスターもそうですし、NHKは防災を伝えることが義務になっている。それはそれで、もちろんいいことで必要なことですが、僕自身は防災があんまり好きじゃない(笑)。線状降水帯が発生することばかり伝えているけれど、線状降水帯の予測は2、3割くらいしか当たらないわけだから、そればかり伝えるのはかえって良くないと思います。
個人的には防災というよりも、自然そのものに興味を持ってもらいたい。自然について考えることが、結果的に防災につながっていくんです。大雨が降っていて、これは危険だと気付くのは自分自身ですよね。だから、自分の五感をもっと大事にしてほしい。天気の伝え手は自分の興味から発信してほしいと思いますし、僕自身も現象を伝えていきたいです、
――今の危機を、どのように伝えたいと考えていますか。
森田 今年の暑さには複合的な原因があります。海水温がずっと高くなっていることや、太平洋高気圧が強かったこと、チベット高気圧が日本付近に張り出したこと、さらに亜熱帯ジェット気流が北に大きく偏って日本周辺で北に蛇行したことなどが同時に起きました。
複合的な現象の中でも最も重要なのは、二酸化炭素が増えていることです。二酸化炭素は地表から放射される熱を吸収して、地表に再放射することで気温を上昇させます。二酸化炭素を含む温室効果ガスの濃度が上昇していることが、間違いなく温暖化の原因でしょう。では、ここ3年の異常な気温の高さは何なのかと問われると、その答えの一つに挙げられつつあるのが、空気が綺麗になったことです。
――空気が綺麗になって、温度が上がっているのですか。
森田 国際海事機関は、2020年に船舶の燃料油の硫黄分濃度規制を強化しました。船舶の排ガス規制ですね。2020年以前に気象衛星の画像を見ると、海の上は船舶による煙だらけでした。煙の微粒子はエアロゾルと呼ばれて、周りの水滴を集めることで雲になります。雲は大気の透過率を下げることで温暖化にも作用していましたが、エアロゾルは太陽を遮ったり反射したりして、地表を冷やす効果もありました。
それが、大気汚染がなくなったことで、二酸化炭素による温度上昇が加速していることが、全部ではないけれども一部影響していると考えられています。以前は大気汚染がひどいと言われていた中国も、電気自動車が普及するなどして都市部の空気は綺麗になっていると聞きます。古い頭のままでいると、どんどん取り残される気がします。天気予報も同じで、防災のことばかり伝えるのはもう古いのではないでしょうか。
――その点から考えると、アメリカのトランプ大統領は、地球温暖化対策の国際的枠組みのパリ協定から離脱したほか、化石燃料産業を推進するなど、温暖化に影響を及ぼす政策を行っていますが、どのように感じていますか。
森田 排ガス規制の問題などと結びつけるのは違和感があります。トランプ大統領の考え方はおかしいと個人的には思いますけど、アメリカ国内の産業や雇用などの複合的な要因があって、そんなに簡単に語れる問題ではないですよね。批判するのであれば、二酸化炭素を出すことを批判すべきだし、二酸化炭素を出さない仕組みのエネルギー革命が必要だろうと思っています。
僕自身が大事にしたい価値は、自由であることです。自由があると同時に、一定のルールがあることが大事です。恐ろしいのは権威主義的な考え方ですね。少数の人間に全てを支配されてしまうような状況を、どうすれば制御できるのかに関心を持っています。天気予報でも定型的な文を読み上げて、防災一辺倒で伝えるだけではなく、線状降水帯の予報は3割程度しか当たらないといったことを、アンダーグラウンドでもいいから一定程度伝えた方が面白いのではないでしょうか。気象予報士はもっと自分で考えて発信した方がいいと思いますね。
(インタビュアー・田中圭太郎)
<森田正光(もりた・まさみつ)氏略歴>
1950年名古屋市生まれ。財団法人日本気象協会を経て、1992年に日本初のフリーお天気キャスターになる。同年、民間の気象会社、株式会社ウェザーマップを設立。親しみやすいキャラクターと個性的な気象解説で人気を集め、テレビやラジオ出演のほか全国で講演活動も行っている。
2005年より公益財団法人日本生態系協会理事に就任し、2010年からは環境省が結成した生物多様性に関する広報組織「地球いきもの応援団」のメンバーとして活動。環境問題や異常気象についての分析にも定評がある。学校法人桑沢学園東京造形大学客員教授、一般社団法人島バナナ協会代表、将棋ペンクラブ審査員。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。
・“ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った! “何となく”で選んでいませんか?効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】
・「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク10月で新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」
・女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市

