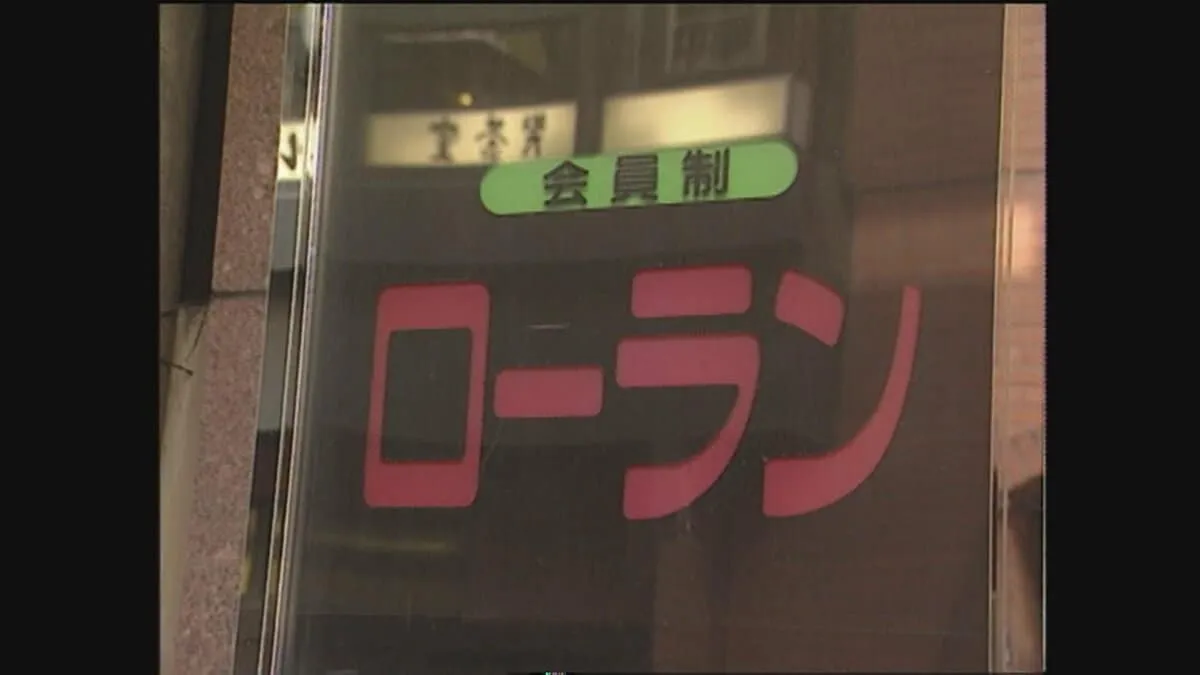
「失われた20年」と呼ばれた平成の時代、東京地検特捜部は、バブル経済の崩壊を契機に、それまで“聖域”とされてきた政治家・大企業・裏社会の癒着に本格的にメスを入れ、大型経済事件を次々と摘発していった。
【写真で見る】接待場所となったノーパンしゃぶしゃぶ店「ローラン」東京・新宿区歌舞伎町(1998年)
1998年1月、特捜部はまず「大蔵省OB」の逮捕、続いて大蔵省本省への強制捜査に踏み切った。それと同時に、第一勧業銀行から「過剰接待」を受けていたノンキャリアの「金融検査官」2人を逮捕した。
「金融検査官」とは、銀行の「不良債権」や焦げ付き融資の有無を厳しく調査する職務であり、バブル崩壊後の金融システム再建において、極めて重要な役割を担っていた。
逮捕容疑は、第一勧銀などの金融機関から接待を受けた見返りに、本来は「抜き打ち」で行うべき「金融検査の日程」を事前に漏洩し、検査に「手心」を加えるなど便宜を図っていたという、重大な収賄の疑いである。
問題となった接待場所のひとつが、東京・新宿区歌舞伎町にあった「ノーパンしゃぶしゃぶ店」だった。大蔵官僚の間では、同店での接待が一種の“ステータス”として持てはやされていたという。
そして事態は、思わぬ展開を見せる。逮捕された金融検査官の元上司で、「ノンキャリアのエース」と称された人物が、突如、自ら命を絶ったのだ──。
捜査の裏側で何が起きていたのか。いまだからこそ明かせる関係者の証言や取材メモをもとに、事件の知られざる舞台裏の一端を描く。
「ノーパンしゃぶしゃぶ接待」
1998年1月26日、東京地検特捜部が「官庁の中の官庁」と称された大蔵省の中枢に切り込んだ。大蔵省が本格的に摘発されたのは、1948年の昭電疑獄以来のことだった。
当時の大蔵省は、現在の金融庁と財務省を合わせた機能を担ってた強大な権限を持った官庁。大蔵省内部では、「まさか、家宅捜索にまで踏み込むとは」との驚きが広がった。
その日、収賄容疑で逮捕されたのは、金融証券検査官室長のMと、金融検査部管理課長補佐のT。いずれも大蔵省のノンキャリア職員だった。
この一週間前には、大蔵省OBで「日本道路公団理事」のIが収賄容疑で逮捕されているが、Iが大蔵省で「初代金融部長」を務めていた際、直属の部下として仕えていたのがMだった。
Mが第一勧業銀行(以下、第一勧銀)のMOF担=大蔵省担当から受けていた「過剰接待」の実態は、世間に大きな衝撃を与えることとなる。
舞台は、東京・新宿区歌舞伎町の「楼蘭(ローラン)」という、いわゆる“ノーパンしゃぶしゃぶ”店。西武新宿駅とコマ劇場(現TOHOシネマズ)をつなぐ路地に面した、6階建てビルの地下にあった。
Mが初めて「ローラン」で第一勧銀から接待を受けたのは、1994年9月下旬。翌月に予定されていた同行への「金融検査」を前にしたタイミングであった。
その際、Mは同行のMOF担にこう依頼したという。
「歌舞伎町のノーパンしゃぶしゃぶに一度行ってみたい。来週のこの日でお願いできないか」
「ローラン」は、掘りごたつ式の席で「しゃぶしゃぶ」を提供するスタイル。
給仕をするのは、膝上20センチのミニスカート姿の若い女性たちだった。追加で5000円〜1万円のチップを渡すと、彼女たちは下着を脱いだ。
天井にはウイスキーボトルが数本、逆さに吊るされており、注ぎ口にグラスを当てると中身が出てくる仕組みだ。
客が水割りを注文すると、女性がグラスを持って立ち上がり、ボトルに手を伸ばして酒を注ぐ。その際、センサーが作動してテーブルの四隅に仕込まれた「通気孔」から風が吹き出し、女性のスカートがまくれ上がる仕掛けになっていた。
この夜のMの飲食代、約4万円は、もちろん第一勧銀が負担した。
「ローラン」は1991年に開店。看板には「会員制 アダルト割烹」と掲げられ、入会には2人以上の紹介が必要。完全予約制で、1日2回の入れ替え制だった。
店舗は地下2階にあり、さらに地下3階には「完全個室」が用意されていた。
「しゃぶしゃぶ」や「すき焼き」には松阪牛が使われ、グレードは「松・竹・梅」の三段階。フォアグラのバターソテー、天然鯛の鯛めしなど料理も「絶品」との評判だった。
この店を接待に利用していたMOF担の一人は、当時こう語っていた。
「女性に渡すチップも加えると、1人あたり5〜6万円はかかった。だが、相手に羽目を外してもらうためには、効果は抜群だった。たとえば1本3000円でペンライトを購入し、こたつに潜りこむと、女性が股間を見せてくれる。こうした破廉恥な遊びを大蔵官僚と一緒に共有することが大事だった。それで“仲間意識”というか“共犯関係”が生まれることで、情報が取りやすくなったことは間違いない。ローランは接待の場としては申し分なかった」
歌舞伎町「ローラン」への家宅捜索
1998年1月27日、大蔵省への強制捜査の翌日、特捜部は「ローラン」への家宅捜索を行った。中国人の女性経営者がパソコンで管理していた「顧客名簿」や、1993年以降の「予約台帳」などが押収された。「ローラン」は漢字では「楼蘭」と表記するが、これは中国新疆ウイグル自治区の地名からとったという。
家宅捜索は6階の事務所から地下の倉庫に至るまで徹底して行われ、女性従業員2人が公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕されている。
差し押さえた資料によって、「約13000人」に及ぶ登録会員のうち、実に「1200人」が金融機関の関係者であることが判明した。
MOF担の接待の場として、「ローラン」が常態的に利用されていた実態が、これによって裏付けられたのである。
中でも意外だったのは、接待の利用回数が最も多かったのが、「第二大蔵省」とも呼ばれたエリートバンクの日本興業銀行(のちにみずほ銀行に統合)だったことである。
日本興業銀行は、バブル絶頂期の1980年代後半、大阪・ミナミの料亭「恵川」を舞台に、女相場師・尾上縫に対して「2400億円」もの巨額融資を行い、当時の支店長が辞任。
「恵川」に出入りしていた黒沢洋頭取も国会で追及を受けた。
今回の接待汚職事件でも、日本道路公団に天下っていた大蔵省OBへの接待をめぐり“エース”と目されていたU常務が贈賄容疑で逮捕されている(のちに略式起訴)。
「ノーパンしゃぶしゃぶ」の利用頻度においても、日本興業銀行は第一勧業銀行、三和銀行、あさひ銀行、野村証券といった他の大手金融機関を大きく引き離していたのである。
ある銀行のMOF担当は「ローラン」についてこう証言した。
「席につく女性は頻繁に交代し、その都度チップが必要だった。結果として1人あたりの費用は5万円を超えることも多かった。ただ、『シェフラー』という店員がチップを立て替えてくれたため、最終的に請求書にまとめて記載され、銀行側が一括で支払うことができた。接待の席では『シェフラー』がMOF担の窓口となって料理のオーダー、指名された女性の配置などを取り仕切っていた」
逮捕された金融検査官のMに話を戻す。
Mは第一勧銀から“ノーパンしゃぶしゃぶ接待”を初めて受けた翌月──1994年10月3日。ついに、第一勧銀のMOF担当に対して「金融検査の日程」や「立ち入り検査の対象支店」といった極秘情報を漏らしたのだ。
第一勧銀のMOF担は、後にこう語っている。
「金融検査の情報は、喉から手が出るほどほしかった。総会屋・小池隆一への焦げ付き融資があり、もし予告なしに検査をやられると、不良債権が表に出るという危険があった」(捜査資料より)
10月11日から始まった金融検査の期間中も、第一勧銀からMへの接待は続いた。銀行近くの「高級寿司店」などで丁重にもてなすなど、第一勧銀は“検査対応”に抜かりがなかった。
ところが思わぬことが起きる。
検査中にMの部下の金融検査官が「小池隆一への融資の焦げ付きは問題ではないか」と強く指摘し、検査報告書に明記するよう求めたのだ。
現場のMOF担レベルでは対処することができず、報告を受けた融資担当常務の寺沢康行常務が対応に乗り出すことになった。
寺沢はかつてMOF担時代にMと顔見知りだったことから、Mに面会して頼み込んだ。
「どうか小池融資案件は取り上げないでほしい。報告書には載せないでほしい」
12月、金融検査は終了。最終的に、総会屋・小池隆一への不正融資は、検査報告書に一切記載されることはなかった。
第一勧銀が小池に対して行っていた「40億円」の融資はすでに焦げ付いており、金融検査で発覚すれば、巨額の不良債権として処理を迫られる恐れがあった。
そのため、第一勧銀はMへの接待を強化していた。結果的に、その目論見は成功したと言える。
年明けの1995年1月、第一勧銀からMへの「アフターフォロー」は続いた。
常務の寺沢とMOF担は、同行の系列企業が運営していた神奈川県大磯町の「レイクウッドゴルフクラブ」にMを招待した。そこで「大変お世話になりました」とお礼を述べた。
この日の接待費用は約7万円だった。
「ゴルフ、旅行、つけ回し・・・・・」は要求型
収賄容疑で逮捕した金融検査官・Mを東京拘置所へ連行し、取り調べを担当したのは、東京地検特捜部の松井巌(32期)だった。松井は一連の「総会屋事件」では、野村証券の酒巻英雄元社長の取り調べも担当していた。
のちに最高検刑事部長、福岡高検検事長を務め、警察庁と協力して北九州市の指定暴力団「工藤会」の摘発に尽力したことでも知られている。
松井はMから「検査情報を漏らす見返りに接待を受けた」と認める自白を引き出した。
Mへの接待攻勢は、第一勧銀の検査前後の1994年10月と、あさひ銀行の検査が行われた1996年6月に集中していたことも判明した。
東京地検特捜部は、金融検査の日程や対象支店を漏らしたり、不良債権を見逃した見返りに接待を受けたり、マンションのあっせんを自ら要求したとしてMを収賄罪で起訴した。
Mが、第一勧銀をはじめとする金融機関から受けた“ノーパンしゃぶしゃぶ店”などを含む接待の総額は、約「810万円」に上った(後に有罪確定)。
東京地検のスポークスマン役、松尾邦弘次席検事(20期)は記者会見でこう強調した。
「Mへの接待はゴルフ、高級料亭、温泉旅行、さらには“つけ回し”もあった。
また本人の要求によるものまで多岐にわたっていた。ほかの金融検査官が第一勧銀による総会屋への不透明な融資に、厳しい指摘をしたにもかかわらず、Mは検査報告書に一切その事実を記載しなかった」
“つけ回し”とは、銀行関係者が同席せず、大蔵官僚だけが飲食し、後日その代金を銀行側が負担する手法である。
またMは、飲食接待のほかにも、武蔵野市の自宅のマンションを購入する際に、あさひ銀行から「約450万円の値引き」を受けていたほか、別の銀行には「歯科治療費」まで肩代わりさせていたことが明らかとなった。
Mは前年の1997年の秋以降、TBSの取材にたびたび応じ、こう語っていた。
ーー接待はワイロにあたるという認識はありましたか?
「なんでワイロになるのか、教えてほしい。我々の重点事項を知りたいこともあるでしょう」
ーー金融検査に手心を加えたことは?
「10人の金融検査官が検査に行けば、物差しは一致しない。裏でこっそりなんてありえない」
ーー銀行担当者側には、検査日程や債券分類に対して依頼する主旨があったのでは?
「非常に際どいとは思う。飲食は皆無じゃないわけで、社会通念上の常識の飲み食いはありますよ…」
Mは逮捕前、TBSの取材に対して「銀行側との飲食はあったが、常識の範囲内だった」と一貫して主張していた。
「つけ回し」と「応報性」
Mとともに、金融検査部管理課長補佐のTも逮捕された。Tは三和銀行や北海道拓殖銀行などから、飲食・土産・観劇など約「450万円」相当の接待を受けていた。
三和銀行には「ミスターMOF担」と呼ばれ、将来の社長候補と言われたHがいたが、Hらは当初「やられるのは第一勧銀が中心だろう」と見ていた。
しかし、三和銀行はあろうことか、大蔵省が東洋信託銀行に対して実施したときの「検査報告書」のコピーをTからひそかに入手していたことが発覚する。
この報告書は「示達書」と呼ばれ、検査対象の銀行の経営状態について詳細に指摘した“極秘文書”であり、漏れることはあってはならないことだった。
また三和銀行はTから飲食店“つけ回し”の請求書を受け取って負担していたほか、Tが知人女性と会食した際にも高級料亭を予約して費用を払っていたことなども明らかになった。
Tが北海道拓殖銀行から接待を受けたのは、大蔵省から拓銀に天下っていた元金融検査官と、検査官OB会「霞桜会」で知り合ったことがきっかけだった。
このOB会は、金融検査部に所属した経験のある元職員の集まりで、毎年2回、都内にある大蔵省の施設で会合を開いており、現職では唯一、Tが世話人を務めていたという。
特捜部の捜査により、MとTに対して接待攻勢をかけていたのは、第一勧業銀行、三和銀行、あさひ銀行、北海道拓殖銀行にとどまらず、東京三菱銀行と住友銀行に及んでいたことも判明する。
Tが好んで要求していたという「ダンスショー」が楽しむことができる「フラメンコレストラン」での接待も含まれていた。
本来、公平かつ中立であるべき大蔵省の金融検査は、MOF担との「ズブズブの癒着関係」によって骨抜きにされていたのだ。バブル崩壊後の金融機関が抱える不良債権処理の先送りの要因にもなった。
とくにMが第一勧銀から総会屋・小池隆一への融資を見逃していたことにより、第一勧銀はその後も100億円近い不正融資を続け、小池の株取引の資金源となった。
小池に対する不正融資を放置したことは、総会屋事件の拡大につながったのである。
東京地検特捜部はそうした「接待」のうち、どのようなケースを収賄罪で立件しようとしたのか、その「判断基準」は何だったのだろうかーー。
熊﨑特捜部長、山本副部長、大鶴班長らが「摘発価値」があるとして、最も重視したのは、「つけ回し」と「応報性」の2点だった。
つまり、「つけ回し」は前にも触れた通り、大蔵官僚が身内だけで飲食した代金を、銀行側に負担させる行為のことだ。
もう一つの「応報性」とは、行為自体の悪質性である。やってはならない違法行為、漏らしてはならない「秘密情報」を、接待の見返りとして実際に漏洩していたかどうかである。
すなわち、「抜き打ち」であるべき検査日程や対象支店という機密事項をMOF担に漏洩した「金融検査官ルート」の捜査は、まさにその「判断基準」に合致していたのだ。
アンタッチャブルとされてきた「官庁の中の官庁」大蔵省への強制捜査は、霞が関にも激震を与えた。強制捜査着手当日の1995年1月26日、三塚博大蔵大臣は辞任に追い込まれた。
また、この日はちょうど「30兆円の公的資金を投入する法案」が国会で審議中だったこともあり、永田町にも激震が走った。
国会議員からは「法案審議中に強制捜査に着手するのは検察ファッショだ」との常套句で、怒りの声が上がった。
このとき、法務省官房長として国会対応にあたっていたのが、但木敬一(21期)だった。
そして、大蔵省との連絡窓口になっていたのが、法務省刑事局長の原田明夫(17期)である。
但木と原田はともに赤レンガ派の「法務官僚」として、政府や大蔵省側の意向を汲みながら対応にあたっていた。
一方で、検察現場を率いるトップの検事総長の土肥孝治や、特捜部を統括する東京地検検事正の石川達紘らは「接待によって金融行政を歪められたという証拠があるなら、やらない理由はない」としていた。
しかし、法務省と検察現場には、次第に捜査の方針をめぐって温度差と軋轢が生じていくーー。
「捜査関係事項照会」とノンキャリアの自殺
強制捜査から2日後の1月28日、大蔵省に激震が走った。
東京地検特捜部から参考人として呼び出しを受けていた、大蔵省銀行局総務課の「金融取引管理官」のO氏が自ら命を絶ったのである。54歳だった。
この日、O氏は午後1時30分に東京地検に出頭するよう求められていたが、指定時刻になっても姿を見せなかった。
検察関係者が各所に連絡を取り続けたが、行方がわからず、午後9時頃になって、東京・渋谷区広尾の官舎で死亡しているのを家族が発見した。
O氏は1962年に大蔵省に入省。いわゆるノンキャリア組でほぼ銀行局一筋に歩み、1995年からは「金融取引管理官」を務めていた。
このポストは大蔵省のノンキャリア職員にとって最高位のポストであり、金融検査官の人事や給与を統括する立場にあった。130人を超える金融検査官のまとめ役であり、現役とOBからなる「霞桜会」の中心的人物でもあった。人望も厚く、「ノンキャリアの星」と呼ばれる存在だった。
平日は通勤のため東京・渋谷区広尾の官舎に暮らし、週末には千葉の自宅に戻るという生活を続けていた。
当時の特捜幹部の一人は背景をこう明かす。
「実は、特捜部が銀行に送付した『捜査関係事項照会』に、『大蔵官僚12人』の名前が、いわゆる“接待リスト“として記載されていた。O氏もその一人だった」
「だが、実際には特捜部は、誰が本当のターゲットなのかを悟らせないように、ダミーの官僚も含めて“五十音順”に並べただけで、順番に意味はなかった。しかし、苗字が『お』で始まるO氏の名前が最初に記載されていたため、O氏本人は“自分が筆頭のターゲットに挙がっている”と誤解してしまったようだ」
この『捜査関係事項照会』の写しが、何らかのルートで大蔵省に渡っていたのだ。
特捜部が銀行側に示した照会文書が、大蔵省側に漏れていた事実は、あらためて銀行と大蔵省の「ズブズブの癒着関係」の根深さを物語っていた。
大蔵省関係者の話によると、O氏はその『捜査関係事項照会』に記されたリストを見て、「自分も嫌疑を掛けられ、逮捕されるのでは」と深刻に受け止めていたという。
当時のMOF担はこう証言する。
「Oさんは、逮捕されたTさんをかわいがっていた。Oさんは中央大学の夜間部出身、Tさんは高卒で共に苦学して、金融検査官の職に就いた。同じ境遇への共感もあったと思う。いずれOさんはTさんを後継にしたいと考えていた」
「Tさんが三和銀行から接待を受けていたことを知り、Oさんはやめるよう忠告した。だからこそ、Tさんの逮捕には大きなショックを相当受けていたことは確かだ」
特捜部の副部長だった山本修三(28期)は、当時の判断を振り返る。
「O氏に関しては、銀行から提供されたタクシーチケットの話はあったが、いわゆる『つけ回し』のような悪質性はなく、立件対象からは外していた。特捜部としては、O氏を逮捕するつもりはなく、むしろO氏への参考人聴取を通じて、キャリア官僚に関する情報を得たいと考えていた」
特捜部として次の捜査の展開は、あくまで「大蔵キャリア」を本丸と定めていた。
そうした中、山本や大蔵ルート班長の大鶴基成は「ノンキャリのO氏に悪質性はない」と判断し、もともと刑事責任を問う意図はなかった。
しかし、O氏は信頼していた部下だったTの逮捕、メディアの過熱報道、そして自らの名前が筆頭に記載された「接待リスト」ーーそれらが重なり、精神的に追い詰められていったとみられる。
一連の総会屋事件、大蔵接待汚職の捜査では、第一勧銀の宮崎邦次元会長など、関係者の自殺が相次いだ。O氏死亡の翌月の2月には、日興証券への「利益要求」で逮捕許諾請求が出ていた大蔵省出身の新井将敬衆院議員がホテルで自殺している。
大蔵省内や官邸からは、「特捜部の捜査はやりすぎじゃないのか」という批判の声も上がりはじめていた。
一方で、世論の大蔵省への怒りは収まらなかった。
大蔵キャリアの「接待づけ」の実態に、国民の不満は頂点に達しようとしていた。とくにノンキャリアの職員ばかりが逮捕され、自殺者が相次ぐ中、大蔵省内部ではこんな疑心暗鬼も広がっていた。
「エリートのキャリア官僚が、責任を逃れるためノンキャリアに責任を押しつけ、検察に情報提供しているのではないか」
「ノンキャリは歯車に過ぎない。高額接待を当然のように受けていたキャリア官僚の責任はどうなのか」
そんな声が、日に日に強まっていった。
O氏が亡くなった28日の夜、事務方トップの大蔵省事務次官・小村武は、橋本龍太郎総理を公邸に訪ねて、ようやく辞意を伝えた。小村については当初、三塚大臣が辞任した段階では「辞任しない」との意向が伝わっていた。
これに対して、自民党の加藤紘一幹事長は「責任の取り方については、国民がじっと見ている。三塚大臣の辞任だけでは決着とはならない」と述べるなど、小村や大蔵幹部が責任を取ることは当然だと強調していた。
小村の在任期間は、わずか6か月で戦後最短の事務次官となった。後任にはいったん大蔵省を卒業して内閣官房の内政審議室長に転出していた田波耕治が異例の復帰となった。
特捜部は「大蔵省OB」の「日本道路公団理事」に続き、「大蔵省ノンキャリア」の「金融検査官」を摘発したが、世論は「大蔵キャリアこそ巨悪の根源」だと受け止めていた。国民の怒りは、高額な接待を受けていたとされる「大蔵省キャリア官僚」に向かっていた。
特捜部は「国民が納得するためには金融行政の実権を握る大蔵キャリアをやらなければ」との強い意識があった。
「ノンキャリアだけを摘発して終わると、検察が大蔵キャリアをかばったと思われる」(元特捜幹部)
世論の後押しを受け、特捜部は大蔵キャリアへの捜査のピッチを上げ、証拠は最終局面へと突入していく。
「大蔵省キャリア」摘発へのネック
バブル期に膨張の一途をたどった銀行の不良債権。
その処理策を銀行に提供すべき立場にあった大蔵省の「金融検査官」が、あろうことか「接待漬け」によって不良債権を見逃し、金融処理の遅れをもたらしたことは明らかだった。
「ノンキャリアの金融検査官は“職務権限”が限定されていて、それに対するワイロの“対価性”すなわち“見返り”の構図が、比較的わかりやすかった。そのため、世間も“摘発価値があった”と受け止めてくれた」(元特捜幹部)
しかし、大蔵キャリアの立件となると、特捜部はさまざまな「雑音」に直面することになる。
一つは「職務権限」の問題だった。
キャリア官僚の業務は政策立案から政官界・財界との調整、さらに職務規定を超える広い意味での「ロビー活動」など多岐にわたっており、明確な「権限範囲」を定義することが難しい。キャリア官僚は、 ノンキャリアのように権限が限定されておらず、接待を受けることも“業務円滑化のための慣例”として黙認されてきた面がある。
こうした風土は、バブル期には、中央官庁のみならず、地方自治体まで広がっていた。
いざ大蔵キャリアを立件するとなれば、接待が「職務権限」と結びついているかどうか、つまり「接待の対価としての具体的にどんな見返りがあったのか」や、「社会通念上許される接待」と「過剰接待」の線引きなど、ノンキャリア以上に、詰めの捜査が求められた。
特捜現場は、摘発の基準をどう考えていたのか。
ある特捜検事はこう振り返る。
「接待を贈収賄事件として立件するしないの判断に重要だったのは、“つけ回し”があるかどうか、また特定の時期に接待が集中しているかどうかだったと思う」
「カネの動き、つまり過剰接待の事実が明確に出てくれば、職務権限につながる趣旨はあとからついてきた。裁判所も“接待は金品授受と同等”とみて、認定してくれると考えていた」
実際、「贈収賄事件」は東京地検特捜部にとって、いわば“十八番”とも言える得意分野であった。重要なのは、捜査段階でそうした贈賄側、ワイロを渡した側の明確な「自白」を引き出すことであった。
「贈賄側の正直な自白と、それを裏付ける証拠が揃っていれば、裁判所に有罪の心証を形成させることができると考えていた」(元特捜検事)
もう一つの「雑音」は、検察という組織特有の事情に関わるものだった。
大蔵省は「国家予算」を分配、管理する“官庁の中の官庁”であり、出身者の大半は東大法学部卒というエリート中のエリート。
その大蔵省の外局にあたる国税庁は、特捜部にとっては1993年の金丸脱税事件など多くの政治家の摘発でタッグを組み、二人三脚で歩んできた重要な「パートナー」でもあった。
国税庁や 各国税局(東京・大阪)の幹部ポストには大蔵省のキャリア官僚が就いていた。
脱税事案では、国税局が情報の端緒をつかみ、検察に告発し、東京地検特捜部が事件化するという「信頼関係」が敷かれていた。こうした経緯から両者には「持ちつ持たれつ」の関係が長年にわたって築かれていた。
また検察庁を退官した“ヤメ検”弁護士に対し、国税が顧問先の大企業を紹介するケースもあった。
さらには法務省が、予算配分を管轄する大蔵省主計局側を接待したり、逆に国税から法務・検察側を接待する例も一部で指摘されていた。
こうした背景から、法務省幹部や検察首脳の一部には大蔵省、とくに「キャリア官僚」への捜査に消極的な声が上がっていたのだ。
「接待もワイロである」
大蔵省接待汚職捜査が佳境を迎えていたある日、東京地検特捜部副部長・山本修三は検察庁舎の地下食堂で、ある法務省幹部とばったり顔を合わせたときのことを記憶している。
「なんとかならないのかよ、と言われたので、どうにもなりませんよ、と受け流したと思う」(山本)
山本は「大蔵省から法務省にいろんなことを言ってきているんだろう」と受け止めた。
ある検察OBはこう語る。
「政治家を摘発できる最強の捜査機関・検察と、予算配分権を持つ最強の行政機関・大蔵省。護送船団行政の時代は、この二つがうまく噛みあうことで、日本の秩序は保たれていた」
「ロッキード事件やリクルート事件を指揮した吉永さん(土肥の前任の検事総長)も、大蔵省を国家システムの中核として守るという大前提は持っていたと思う。とは言え、吉永さんが検事総長の時代に大蔵省汚職が発覚していたとしても、贈収賄という実質犯の証拠が出ている以上、“大蔵キャリアを接待で立件するのは辞めろ”とは言わなかっただろう」
実際、東京地検検事正の石川達紘(17期)や特捜部長の熊﨑勝彦(24期)には「接待」を「ワイロ」とみなして、贈収賄事件を立件した捜査経験もあった。
石川は1986年、通産省のキャリア官僚が業者から340万円の接待を受けて便宜をはかっていた「撚糸工連事件」で、悪質な「つけ回し」の実態を摘発している。同事件ではロッキード事件以来10年ぶりに国会議員が摘発されている。
また熊﨑は、1988年の「総理府汚職事件」で、元広報担当参事官を100万円余りの接待で立件。さらに1989年の「リクルート事件」では、「飲食接待」や「ゴルフ旅行」など130万円余りの接待を受けた労働省(現、厚生労働省)の官僚を収賄罪で摘発している。
今回の大蔵省接待汚職では、それら過去の事件をはるかに上回る規模の接待が行われていた。
こうした前例を踏まえ、「接待もワイロである」という認識は、捜査実務において、すでに検察内では常識となって根付いていた。「刑法197条」に規定されている収賄罪は、「ワイロを現金だけでなく、人の需要・欲望を満たす、あらゆる利益」と定義しているからだ。
「現金さえもらわなければ、刑事責任を問われることはない」というのは、公務員側の勝手な解釈に過ぎなかった。
熊﨑は筆者にもこう語っていた。
「接待に関しては、検察よりも裁判所の方がよほど厳しく捉えている。キャッシュが出てきてなくても、裁判所は“接待イコール金品授受”とみなしている。だけど、特捜部は“単なる接待”だけでは立件しない。きりがないやろ」
「“つけ回し”があることと、その公務員しか持ちえない秘密情報の漏洩といった行為が伴っている“接待プラスアルファ”がなければ、やらないよ」
捜査着手の「順番入れ替え」
1998年2月、大蔵キャリア官僚の証拠はほぼ固まり、捜査着手に向けての準備は整いつつあった。
東京地検検事正の石川は、かつて定期的に昼食を共にしていた同期の法務省刑事局長・原田や、疑惑が取り沙汰されていた大蔵省審議官・杉井孝らとの会合を、特捜部の接待汚職捜査が本格化するのにあわせて、取り止めたという。
一方、水面下では特命班の粂原研二(32期)らが、大蔵省OBの国会議員に関する捜査を進めていた。
捜査対象となったのは大蔵省出身の新井将敬衆議院議員。株取引をめぐって日興証券に利益要求の疑いが持たれていた。
戦後の東京地検特捜部が手掛けた多くの疑獄事件では、しばしば「最終ターゲット」として国会議員を立件し、捜査を終結させるスタイルが多かった。
熊﨑ら特捜部は、現職の大蔵キャリアに着手したのち、仕上げとして新井将敬を立件し、一連の大蔵省接待汚職事件を着地させる方針で捜査を進めていた。
一方で、筆者のもとにはこんな情報が伝わってきていた。
「法務省が『新井事件を先に着手してくれ』と検察に要請してきたようだ。どうやら捜査の順番が入れ替わったらしい。法務省は政治家ルートの新井事件に世間の注目を集め、特捜部には大蔵キャリアをやらせないつもりかも知れない」
特捜部は1月26日に大蔵省の強制捜査に着手し、まずノンキャリアの金融検査官を摘発していた。
関係者によると、実はその直後、法務省幹部から検察首脳に対して「大蔵省汚職捜査は3月末をもって終結する」との意向が示された節があった。
ある検察関係者は当時をこう振り返る。
「国会議員の新井を立件すれば、当然ながら世間の関心はそこに集中する。特捜部も新井ルートの捜査に人員を割かれ、手間もかかる。そうなると後回しにした『大蔵キャリア』の摘発は「3月一杯」という期限を考えると“時間切れ”でうやむやとなる。立件不可能となる。法務省は、そこまで考えたのではないか」
法務省幹部の「順番入れ替え」の要請に対して、特捜部長の熊﨑は「やはり新井は最後にしたい」と検察首脳を通じて反対したというが、最終的には受け入れた。
つまり、法務省は「大蔵キャリアの摘発」に消極的だった。
ノンキャリアの金融管理官の自殺に加え、その前には第一勧銀の元会長が総会屋への利益提供事件の捜査中に自殺するなど、相次ぐ事件関係者の自殺に神経をとがらせていた。
大蔵省と向き合っていた法務省は、大蔵省との関係をこれ以上、悪化させることは避けたかったのだ。
要するに、法務省としては特捜部が「国会議員の新井将敬を立件すれば時間切れとなり、特捜部は大蔵キャリア摘発には執着しないだろう」との打算があったと見られる。
そうした構図の中で、法務省は検事総長の土肥、東京地検検事正の石川を説得し、「大蔵キャリアルート」と「新井将敬ルート」の捜査の順番を入れ替えるよう要請したのである。
そして検察首脳の意向を受けた特捜部は、まず新井将敬事件の強制捜査に踏み切った。
しかし、この判断の先には、誰も予想しなかった事態が待ち受けていたーー。
(つづく)
TBSテレビ情報制作局兼報道局
ゼネラルプロデューサー
岩花 光
《参考文献》
村山 治「市場検察」 文藝春秋、2008年
村山 治「特捜検察vs金融権力」朝日新聞社、2007年
村串栄一「検察秘録」光文社、2002年
読売新聞社会部「会長はなぜ自殺したか」 新潮社、1998年
産経新聞金融犯罪取材班 「呪縛は解かれたか」角川書店、1999年
熊﨑勝彦/鎌田靖「平成重大事件の深層」中公新書ラクレ、2020年
伊藤博敏「黒幕 裏社会の案内人」小学館、2014年
・エアコン「1℃下げる」OR「風量を強にする」どっちが節電?「除湿」はいつ使う?賢いエアコンの使い方【ひるおび】
・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】
・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】

