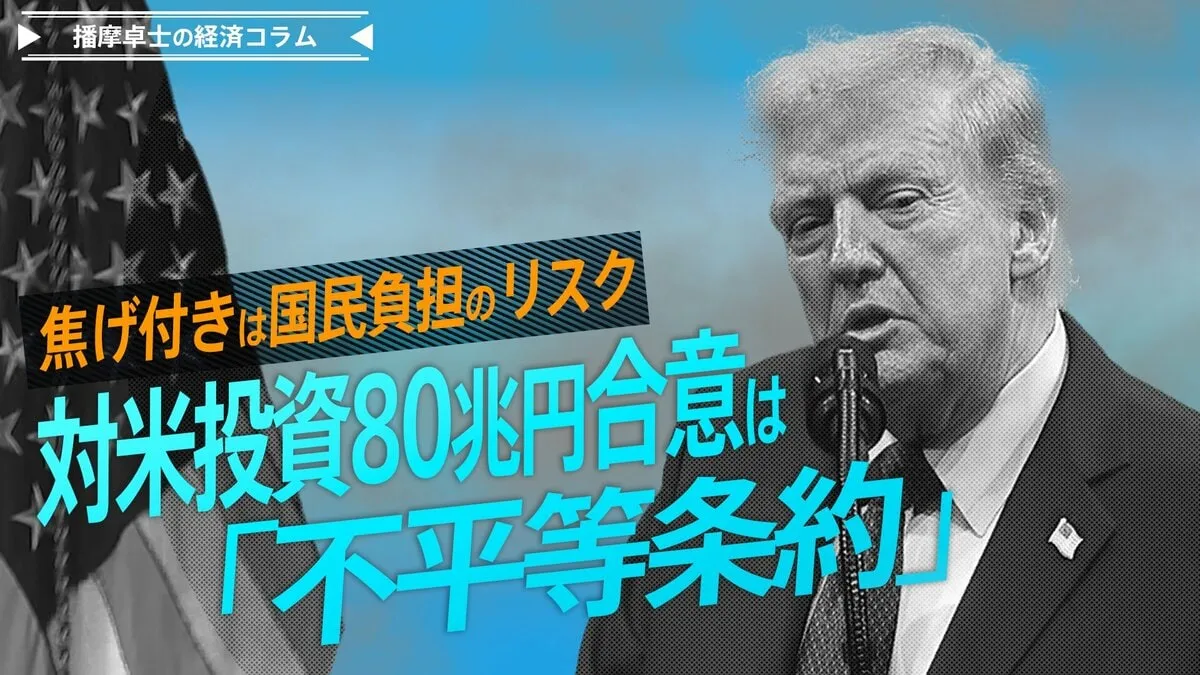
聞けば聞くほど理解できない合意です。相互関税や自動車関税を15%にしてもらうために結んだ80兆円に上る対米投資の合意です。アメリカ側の求めに応じて赤沢大臣が署名した覚書を読めば、これまでに例を見ない、いわば「不平等条約」であることがわかります。決めるのはすべてアメリカ、日本はお金を出すだけで、焦げ付きのリスクは日本国民が負う形です。
【写真で見る】対米投資80兆円合意は「不平等条約」、焦げ付きは国民負担のリスク
決めるのはアメリカ、おカネは日本
9月4日に赤沢大臣とラトニック商務長官が署名した覚書によれば、まず、投資案件は、アメリカの商務長官が議長を務める「投資委員会」の推薦の中から、トランプ大統領が選ぶとしています。
大統領への推薦の前に、日米両国から指名される「協議委員会」と協議すると、言い訳のように書かれていますが、決定前に日本側の意見を聞く場を作っただけで、要は投資案件はアメリカが決めるというのです。資金の出し手である日本が投資先を選べないだけで、まず十分、不平等条約でしょう。
覚書は、大統領の決定から45日以降に、日本が「指定口座に資金を拠出する」と記されています。ほとんどATMのような扱いです。
拒否したら関税引き上げも
では、日本は断ることはできないのでしょうか。覚書には、「日本が独自の裁量で資金を提供しないことを選択できる」と一応は書いてあります。しかし同時に、「日本が覚書を誠実に履行し資金提供を怠らないでいる間、米国は日米合意の関税を引き上げる意図は持たない」と明記していて、普通に読めば、「日本が拒否した場合は、関税を引き上げる」と言っているようなものです。
資金を提供する側が、こんな脅し文句が書かれた文書に署名するなどというのは、長く日米摩擦を取材した身としては、とても信じられない出来事です。投資はトランプ大統領の任期が終わる2029年1月19日までに行われ、総額は5500億ドル、日本円で80兆円と巨額です。
「投資促進」と言うより「公的金融支援」
投資と聞けば、まず民間企業によるものをイメージします。自動車や電機をはじめ多くの日本企業がこれまで工場建設など対米投資を行い、雇用や現地経済に貢献してきました。ですから、今回も「対米投資拡大」と聞いた時に、同じようなものだろうと想像し、同時に政府がどうコミットするのかと首をかしげたのですが、合意内容を見る限り、これまでの対米投資計画とは似て非なるものだとわかりました。
日本企業の対米投資を促すようなものではなく、アメリカの求めに応じて日本が公的な金融支援をする枠組み、言ってみれば、援助に近いものと言えるでしょう。
国際協力銀行の出資、融資、融資保証が中心
では、どのような形で金融支援を行うのでしょうか。トランプ大統領が案件を決めると、そのプロジェクトを管理・統治する特別目的事業体(SPV)が設立されます。その上で、プロジェクト単位のSPVに対し、政府系金融機関である日本の国際協力銀行(JBIC)が、出資したり、融資したり、さらには融資保証を行います。融資保証とは、日本の民間銀行などが、このSPVに融資した場合に国際協力銀行が保証を行うという意味です。
SPV、つまりそのプロジェクトがうまく進めば、融資は返済され、その間の貸付利子がJBICや邦銀に入ります。プロジェクトが順調なら、コストを上回る利益も出ます。
利益は、融資が返済されるまでは、日米が50%ずつ、融資返済後は日本が10%、米国90%で分配するとしています。利益配分1対9の算定根拠は明記されていませんが、赤沢大臣のこれまでの説明からすると、JBICの出資比率が10%程度に留まることを前提にしているようです。
経済安保促進の観点も
プロジェクトの対象として、半導体、医薬品、金属・重要鉱物、造船、パイプラインを含むエネルギー、AI、量子コンピューティングが、具体的に覚書に挙げられており、経済安全保障に焦点を当てています。
生産施設などの立地がアメリカだとしても、それが米経済のみならず、日本の経済安全保障にも貢献するのであれば、日本が資金を出す意味があるという考え方なのでしょう。その意味で、今回の合意は、経済安保という新しい時代のニーズも踏まえた、新しい経済協力の在り方を示した面もあると言えるかもしれません。
焦げ付きは国民負担のリスク
しかし、結果的にプロジェクトがうまく行かないケースも、想定しておく必要があるでしょう。プロジェクトが失敗すれば、利益の分配どころか、日本側が拠出した出資や融資が焦げ付くリスクがあることは明白です。
とりわけトランプ大統領が、経済合理性よりも政治的アピールを狙って、短期間に次々とプロジェクトを決めれば、なおさらです。その際には、融資保証した分も含めて、国際協力銀行が焦げ付きを被ることになるのです。
国際協力銀行の資金の原資は、財政投融資。郵便貯金や年金の資金が間接的に投入されているのですから、焦げ付きは、最後は、日本国民の負担になってしまいます。そのリスクにさらされるのが、総額80兆円ということになります。果たして、石破政権は、最悪の事態を想定した覚悟があって、この覚書に署名したのでしょうか。
アラスカLNGが本命か
こうした中、東京電力と中部電力が設立した火力発電の会社・JERAは、11日、トランプ大統領がこだわるアラスカ州の液化天然ガス(LNG)事業からの、調達の検討を始めると発表しました。開発を進めるグレンファーム社との間で「関心表明」の意向書を締結しました。「関心表明」には、法的拘束力はないとのことですが、これまで日本側は、1300キロにも及ぶ長いパイプライン建設が必要なこのプロジェクトには、コスト面からも、慎重な姿勢を示してきており、はっきり「関心」、つまり前向きな姿勢を示したことは、大きな転換です。その背景に、今回の合意にある「公的な支援」の存在があることは明らかです。
時を同じくして、ラトニック商務長官は、11日、CNBCのインタビューにアラスカLNG開発プロジェクトが、日米合意の投資対象になるとの見方を示した上で、「1000億ドル(約15兆円)のプロジェクトだ」と述べました。日本は、外堀を埋められるように、いわば「拒否権なし」の形で、このプロジェクトに参画することになるのでしょうか。
自動車最優先でまとめられた合意
今回の対米投資合意は、高率の輸入関税、とりわけ基幹産業である自動車の関税を少しでも下げるために、赤沢大臣を筆頭に急いでまとめたという経緯があります。もちろん、急がなければならない理由があったわけですが、一方で、合意直後には、合意内容を確認する文書すら作っていないという杜撰な面もありました。
この間、関税15%への引き下げのメリットと、対米投資80兆円のリスクがきちんと国民の前に示され、そのバランスが吟味されることもありませんでした。「関税より投資」などという石破総理の、曖昧な言葉だけが先行し、「投資」の中身は、未だに藪の中です。
退陣を表明した石破政権、「日米関税合意」を成果と胸を張りますが、そのツケの大きさは、まだ見えていません。ツケの存在が国民に示されていないことが、何より問題なのです。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)
・“ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った! “何となく”で選んでいませんか?効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】
・「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク10月で新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」
・女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市

