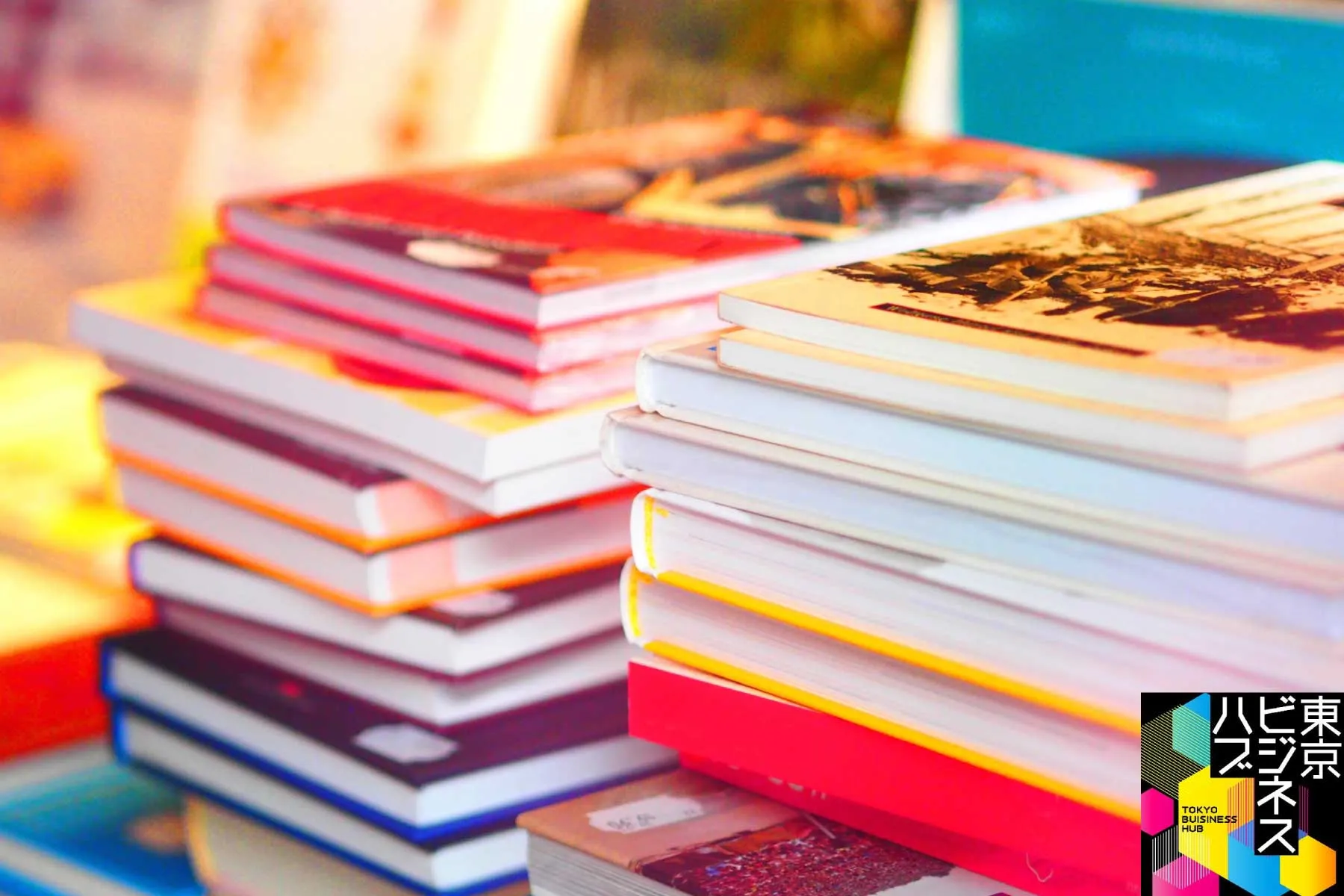
電子書籍の普及や「読書離れ」などで減少の一途をたどる書店業界。しかし、欧米ではZ世代やミレニアル世代を中心に、「リアル書店」が復活の兆しを見せています。一体何が起こっているのか? そして、日本への影響は? 書籍を巡るオンラインと実店舗の状況を、音声プロデューサーの野村高文が語ります。
<東京ビジネスハブ>
TBSラジオが制作する経済情報Podcast。注目すべきビジネストピックをナビゲーターの音声プロデューサーである野村高文と、週替わりのプレゼンターが語り合います。今回は野村による音声コラム、2025年1月5日の配信「欧米で“リアル書店回帰”の動き。一方、日本では・・?」を抜粋してお届けします。
「若者はリアル書店に行かない」は間違い?
昨年10月にイギリスの書店協会が行った調査データによると、Z世代とミレニアル世代などの若年層はその上の世代よりも、書店で本を購入する可能性が高いということがわかりました。Z世代は今の20代、ミレニアル世代は今の30代を中心とする世代です。
具体的には、オンラインではなく実店舗で本を購入すると回答したZ世代が49%で、ミレニアル世代が56%。この2世代のほぼ半数が実店舗で本を購入すると回答しました。上の世代と比較すると、大体40代~50代ぐらいのX世代は37%で、1946年から64年生まれ(ベビーブーマー世代)は31%でした。この調査をまとめると、年長世代はリアル書店に行く習慣があって、若い世代はそういう習慣がないという言説が、実は違う可能性があることがわかりました。
このデータをもとにイギリスの有名雑誌『ガーディアン』は「若い世代はSNSに夢中で本を読まなくなったというような先入観は疑問を持つべきだ」と報じています。一方で、その記事に登場するイギリスの書店員たちによると「この結果は驚くようなことではない」「ここ数年、書店員のおすすめを求めて店に来る若い読者が急増している」とコメントをしています。
『ブックトッカー』とZ世代が思うリアル書店の魅力
この背景についてガーディアン誌は、アルゴリズムとオンライン小売業者への抵抗が少なからずあると分析しています。これが面白い分析で、イギリスの若い読書好きの人たちに本を知ったきっかけを聞くと、ブックトッカー(BookToker)でした。
ブックトッカーとは、TikTok上で本を紹介するインフルエンサーのことで、そのコンテンツ自体は『ブックトック』と呼ばれています。ブックトッカーの紹介をもとに、実際の購買行動につながるという現象が起こっています。
日本ではまだあまり聞かない言葉ですが、私が昨年アジア約5か国へ出張で訪れた際に、どの地域の書店にも「ブックトックコーナー」が展開されていました。
前述のガーディアン誌は、ブックトックが本を選ぶ上で大きな影響力を持つ理由に「オンライン疲れ」を指摘します。読者がコンテンツやアルゴリズムに日々さらされて生き続けていることで、その習慣に飽きたり、疲れてきたりしていると推測されているようです。
その記事にコメントした27歳の女性によると「本屋で店員と話をして、その人の意見を聞いたり、自分の好きな本について話したりするのは、アルゴリズムに基づいて本を選ぶよりずっと楽しいと思う」というコメントをしていました。アルゴリズムは自分の好みに最適化した本を提案してきますが、それよりもリアルの書店に行って店員さんと話して、偶然性の中で本を選んでいくということに魅力を感じているという動きが広がっています。
アメリカでも起きている“リアル書店回帰”
イギリスだけではなくアメリカでもリアル書店回帰という動きは起きています。 2023年3月の記事によると、アメリカ最大のリアル書店チェーンであるバーンズ・アンド・ノーブルのCEOは、総店舗が30店ほど増えるとインタビューで答えています。リアル書店が増えるとは意外です。
なぜならアメリカにはAmazonの存在があり、日本以上に国土が広いため、通販で物を買う傾向が高いからです。Amazonが台頭した影響で、2011年には書店チェーン2位だったボーダーズグループが経営破綻しました。バーンズ・アンド・ノーブルも2019年にはヘッジファンドに売却しており、経済的な苦境を味わっています。
一方でコロナ禍を機に、書店ブームや読書ブームが再び高まっています。スマホやタブレットなどでの動画視聴も普及していますが、常に画面を見続けることに疲れたり、飽きたりすることもあります。その中で紙の本に対する人気が比較的上がっていきました。2021年のアメリカ市場における紙の書籍販売は、8億2800万冊と調査開始以来過去最高になったというデータもあります。そんなに回復しているんだと結構驚きました。
また、電子書籍と紙の書籍の割合を比べても、実は電子書籍の割合はさほど高まっていません。電子書籍は10年以上前の2013年に全体の28%まで上昇しましたが、実はそれ以降は下落しています。紙の書籍の方がシェアが高まっているということもあり、今は電子書籍が約20%で紙が約80%ぐらいです。つまり紙の書籍の人気が依然として強く、その中でオンラインではなく、リアル書店の人気が再び蘇ってきたことがアメリカの状況です。
日本でリアル書店は減少の一途
一方、日本では残念ながらこの動きは現状では起きていません。ただ、出版物自体のマーケットサイズは、最も小さかった2019年から徐々に回復してきました。おそらくコロナの影響といわれており、巣ごもりの中で漫画などのコンテンツを味わう時間が増えて、人々が流れていきました。
これにも面白いデータがあります。日本の書籍のマーケットサイズは約2兆円といわれていますが、そのうちリアル書店を経由して買った比率とインターネットを経由して買った比率を比べてみると、初めてインターネット経由がリアル書店経由を逆転したのは2022年でした。逆に言えば、それまではリアル書店の方が多かったようです。
ただし、日本ではリアル書店回帰どころか書店の売り上げは減り続けています。これは書店の店舗数にも反映されています。
2000年頃、出版業界が非常に元気だった頃は、書店の数は約2万2000店舗と言われていました。それが2017年には1万2500店舗とだいぶ減ります。2023年は1万900店舗。およそ四半世紀で半減ということです。皆さんも自分の町から書店が消えてしまったという経験をされたと思います。都市部にいらっしゃる方でも定期的に行っていた書店がなくなり不便になったと感じる方も多いと思います。
「リアル書店回帰」は日本でも起こりえるのか?
理論的には、欧米で起きているようなオンラインからオフラインへの回帰、いわゆる“リアル書店回帰”は、ビジネスの流れとして日本でも起こり得ると考えられます。しかし、それがいつ起こるか、また、日本ではどのようにして広まっていくかは、まだ予測が難しく、現状では起きる兆しがありません。
「オンラインが行き過ぎた状況」へのカウンターとしてのリアル書店回帰というのは、きっと日本でも起きると思いつつも、だからこそ書店業界としての今は、粘り時なのだ考えられます。
<野村高文>
音声プロデューサー・編集者。PHP研究所、ボストン・コンサルティング・グループ、NewsPicksを経て独立し、現在はPodcast Studio Chronicle代表。毎週月曜日の朝6時に配信しているTBS Podcast「東京ビジネスハブ」のパーソナリティを務める。
・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】
・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】
・【検証】「布団の上に毛布」が暖かい説 毛布は布団の「上」か「下」か 毛布の正しい使い方【Nスタ解説】

