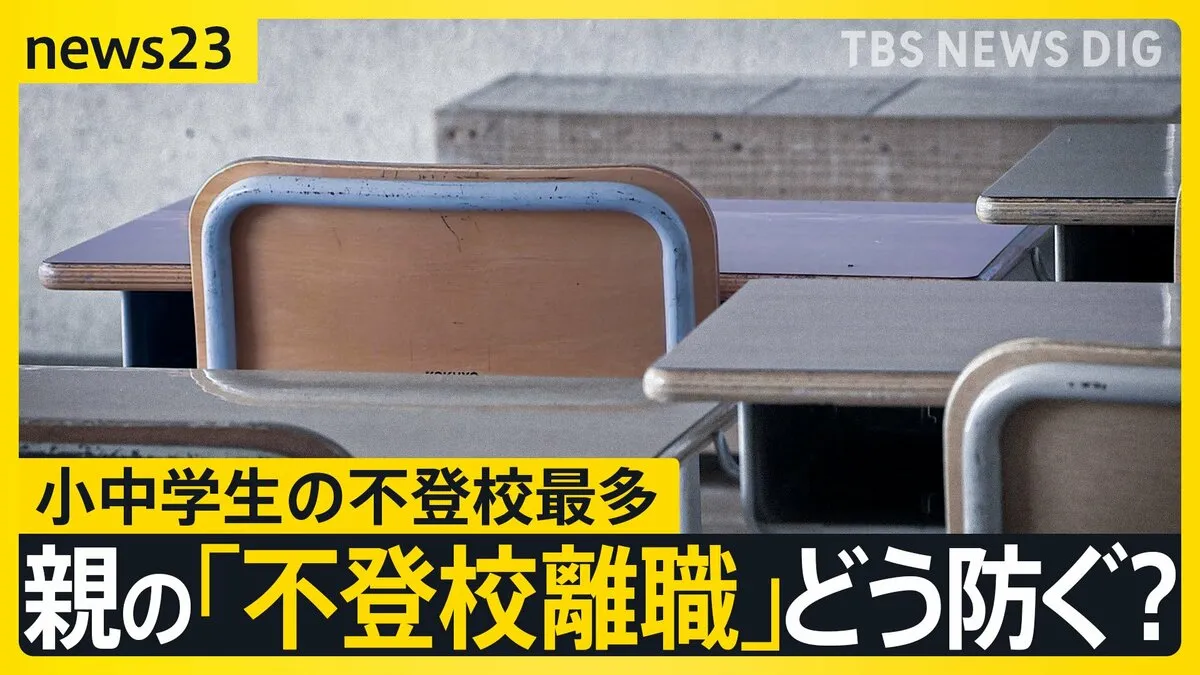
不登校の状態にある小学生・中学生が過去最多となったことが分かりました。さらに、不登校の子どもを持つ親の4人に1人が離職や休職をせざるを得なかったという調査結果も。子どもにも親にも、「頼れる場所」が求められています。
【アンケートによると…】子どもの不登校で37.5%の人が「早退・遅刻・欠勤が増えた」
「学校行きたくない理由わからない」不登校過去最多35万人超
都内にあるフリースクール「かなめのもりのがっこう」に、この日集まったのは、子どもの不登校に悩む親たちです。
こちらの女性は小学生の娘が友人関係に悩み、不登校に。
娘が不登校の保護者
「行き渋りの中で、何とかご褒美みたいなものをちらつかせながら、頑張って行かせちゃってたんですけど、9月から全く行かなくなったっていう感じで」
一方、こちらの男性は、子どもが学校に行きたがらない理由が明確にわからない、と頭を悩ませます。
小学生の父親
「学校には行きたいんだけども、『ちょっと教室に入りたくない』っていう」
かなめのもりのがっこう 井上創代表
「『行きたくない』って言ったときに、立ち止まれるかどうかってすごく大事」
29日、文部科学省が発表した調査結果では、小中学校の不登校の児童生徒は12年連続で増加。過去最多の35万3970人となりました。これは、30人の学級に1人は不登校の子どもがいる割合です。
井上代表
「最近の例だと、隣の子が強く怒られてるのが耐えられないという子もいますね。教室の中で注意されている子がいることが、その姿を見るのもちょっと耐えられない」
親が直面“不登校離職”の現実
ほかにも、「学校生活にやる気が出ない」「生活リズムの不調」など、理由は様々。柔軟なサポートが求められる親にも、負担がのしかかります。
小学生の父親
「答えがないんですよね、本当に。だからって手放しにできないし、やれることをやるしかない。子どもがそうなった時に、親も相当ストレスを感じる。親たちのケアもないんですよね、自分で調べて自分でケアする」
井上代表
「お父さんとお母さんが安心安全を感じていることが、子どもにとっての安心安全だろうし、お父さんお母さんが笑顔で自分に接してくれるっていうことが、子どもの幸せ」
不登校の子どもを持つ親、約400人を対象に行った調査では、4人に1人が離職や休職をせざるを得なかったという結果に。この調査を行ったNPOの代表は、「働きながら不登校の子どもを支えられる社会づくりが必要だ」と訴えます。
企業向けのセミナーでは...
NPO法人キーデザイン 土橋優平代表
「子どものことで悩んでいるのは親御さんなんですね。『何でこうなったんだろう』と最終的に自分自身を責めるようなことが多い。不登校は親のせいでも、子どものせいでもありません。『私に何かできることはないかな』と、そういう視線で、ぜひ親子に関わってもらえるとうれしいです」
4人に1人が“不登校離職・休職” 企業にも迫る対応
喜入友浩キャスター:
改めて、今はどういった状況なのか、NPO法人キーデザインによる不登校の子どもを持つ保護者に行ったアンケート結果を見ていきます。
37.5%の人が「早退・遅刻・欠勤が増えた」と答え、また4人に1人が「退職」や「休職」を選択したということです。
その背景について、不登校の親子を支援する活動を行っている、NPO法人キーデザインの土橋優平代表理事によりますと、「もっと子どもに集中した方がいいと考え、仕事から離れる決断をする親が多い」と話しています。
小川彩佳キャスター:
4人に1人がいわゆる「不登校離職・休職」という状態になってしまっているこの実情について、どう考えますか?
トラウデン直美さん:
もちろん、お子さんが一番と考えての選択だと思いますが、自分自身の仕事に影響が出てしまうっていうことのストレスも親御さんにはきっとあるでしょうし、それが回り回ってお子さんにも影響しないとも限らないと思います。
いろんなケースがあると思うので一概には言えないですけれども、親御さんが仕事を続けながらお子さんの居場所が学校以外にもあるという状況が必要だろうと思います。
一つの解決の案として、地域コミュニティで子どもを見てくれるような場所が何個も何個もある。フリースクールもそうですし、地域の方々が集まるようなところにお子さんも一緒に行くなど、いろんな形で社会全体で親御さんとお子さんをサポートしていかないといけないなと思います。
小川キャスター:
孤立しない・させないということが大事ですし、親としては「何とか子どもに寄り添っていかなければ」と全神経を集中しようとする。そうした親の愛情は尊いものだと思いますけれども、そこの中で親御さんが疲れてしまうと、お子さんたちも疲弊してしまって、お子さんは親がもし離職してしまったら「自分のせいで仕事を辞めてしまったのではないか」と、逆に自分を責めてしまうということにも繋がりかねないですよね。
喜入キャスター:
親にも負担感というのがもしかかってきます。それをいかに減らすかということで企業も努力が求められますけれども、土橋さんは、「柔軟な勤務形態や相談窓口の設置などで働きやすい環境を整えることが求められる」とおっしゃっています。
トラウデン直美さん:
ただ、なかなか家庭内のことを職場に相談するというのもハードルはちょっとありますよね。
喜入キャスター:
言いづらい・相談しづらい内容だからこそ、聞いてあげる・気づいてあげるということも大事だと思います。土橋さんは悩んでいる従業員に気づく方法として、「子どもが不登校になると、朝起きるのがつらくなるケースがある。小・中学校に通う子どもを持つ従業員の遅刻が増えている場合は、声をかけてみて」と呼びかけています。
トラウデン直美さん:
お子さんを持つ家庭の方に対してのサポートというのはしっかり必要だとは思います。ただ、それによってお子さんのいない方々がしわ寄せを感じてしまって、そこで軋轢が生じてしまうのも要らぬストレスをうんでしまうと思うので、どんな方でもあえて理由を言わずとも、休みやすい職場環境が実現できたらいいのかなと思います。
小川キャスター:
心の健康を保って自分の人生を大切にする、親御さんご自身の自己肯定や健全な子どもとの距離感というのも大切なのではないかと感じます。
今、重荷を背負っていると感じられている方は決して抱え込むことなく、文部科学省やそれぞれの自治体など、様々な窓口で相談できる電話番号などもありますので、ぜひ調べていただいてそうしたところに相談することも考えてみてください。
========
<プロフィール>
トラウデン直美さん
Forbes JAPAN「世界を変える30歳未満」受賞
趣味は乗馬・園芸・旅行
・「インフルにかかる人・かからない人の違いは?」「医師はどう予防?」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】
・【全文公開】トランプ大統領「日本という国を尊敬」日米首脳会談で「日本もかなり自衛隊や防衛を増加すると聞いている」など冒頭発言
・「息子のあんたが責任を持って殺しなさい」8年間の孤独な介護の末、91歳の母親の命を絶った男性の苦しみ “介護殺人”を防ぐには【news23】

