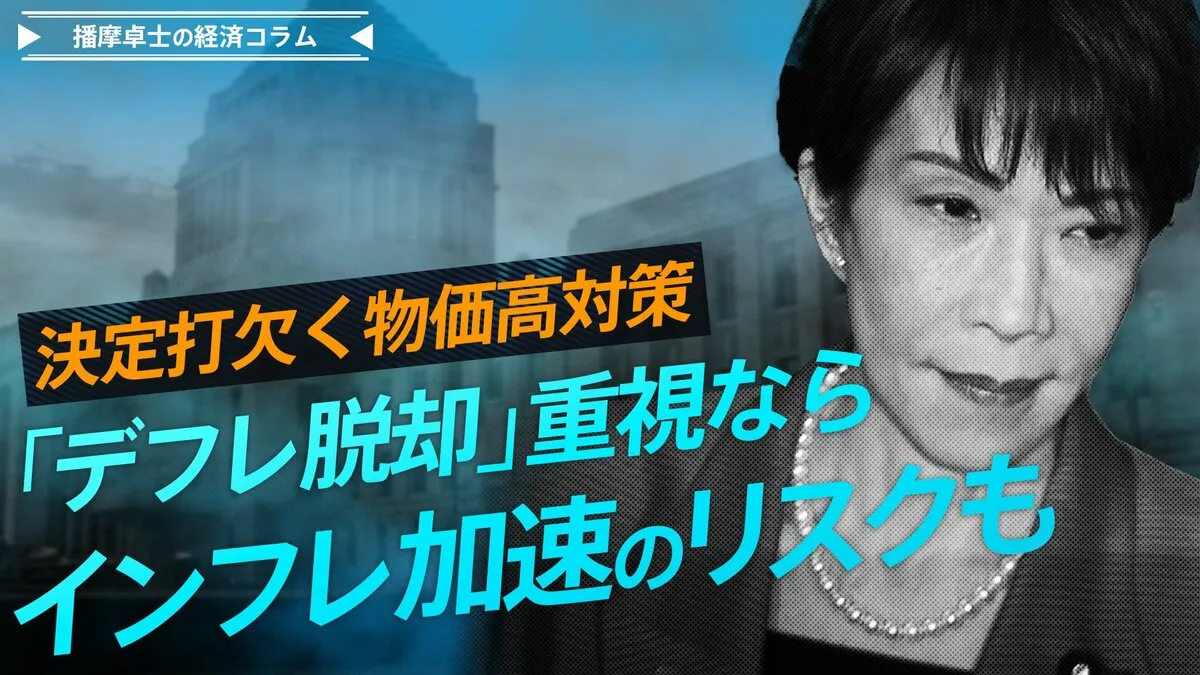
高市政権による経済対策づくりが本格化しています。夏の参議院選挙以来、国民の関心が高かった物価高対策では、消費税減税や現金給付を見送ったことから、大きな柱になるものがなく、パンチの弱い内容になりそうです。経済対策での高市総理の関心は、戦略的な投資などに傾いているようにも見え、物価高対策を最優先に求める世論とは、少しずれつつあるように思えます。
【写真を見る】決定打欠く物価高対策、「デフレ脱却」重視ならインフレ加速のリスクも
ついにガソリン暫定税率廃止
政府与党で検討が進められている経済対策のうち、物価高対策で一番の目玉になるのが、ガソリンの暫定税率廃止です。夏の参議院選挙の結果を受けて、もはや1リットルあたり25.1円のガソリン暫定税率を維持することは、政治的に困難になっていました。高市政権が最終的に「12月31日廃止」に踏み切ったことは、率直に評価すべきでしょう。
家計1世帯あたりのガソリン消費量は平均で年430リットルなので、1年間で1万800円の減税になります。現在は1リットル10円の補助金が出ているので、現状と比較すれば1リットル当たり15.1円、年間消費では1世帯当たり6700円の負担軽減となります。経過措置として13日からは5円補助金が積み増されるなど、すでに店頭でのガソリン価格は下がり始めていて、対策の中では即効性があるものです。
もっともガソリン暫定税率廃止を巡っては、(1)車保有の是非や運転距離によって恩恵の差が大きいこと、(2)原油価格がすでにピーク時より大きく下がっていること、(3)さらに地球温暖化への対応に逆行することなどから、反対する意見も根強くあります。
しかし、1974年に2年間の時限措置として導入された「暫定税率」が、一般財源に形を変えた上に、51年もの長きにわたって、手付かずであったこと自体、政治の在り方としては誠実さを欠いていたわけで、国民の怒りの対象になるのは当然のことだったと言えます。いったん廃止というのは、当たり前のことです。
電気ガス代補助や自治体交付金
また、お馴染みの電気・ガス代への補助金を、冬季に限り再び支給することも固まりました。高市総理は、「補助を深掘りする」としており、補助額の積み増し額が焦点です。
さらに、重点支援地方交付金として、各自治体にお金を配り、地域の実情に合わせた物価高対策がとれるようにするとしています。具体的には、低所得者向け給付や、プレミアム商品券の発行、さらには「おこめ券」の配布などが想定されています。重点支援地方交付金は、支援の現場である地方に裁量を与えることですばやい実施が期待できるわけですが、その一方、その内容には目新しさはありません。
そもそも夏の参議院選挙で石破前政権が掲げた現金給付が否定された上、食料品に対する消費税減税についても、高市総理が早々と持論を封印したことから、本命不在の対策づくりになった感があります。
本来なら、年末に所得税減税を行うとか、石破政権が提案した一人2万円より大きな規模の給付を検討するなどの余地もあったと思いますが、選挙後の長い政治空白のツケで、こうした検討の時間は無くなった形です。
コメ政策は「価格高騰放置」に転換
今回の対策作りで最も理解に苦しむのが、今の物価高の大きな要因であるコメ価格高騰への対策がなく、逆に、今の高騰した価格を放置しようとしていることです。鈴木新農水大臣の下で、コメ増産方針は事実上撤回され、来年には備蓄米を、逆に、積み増す方向で動いています。
今年9月の全国消費者物価の総合指数は、前年同月比で2.9%の上昇でした。このうちコメ類の押し上げ寄与度は0.39ポイントもあります。これにおにぎりや外食などの値上がりも加えれば、相当なウエイトになります。1年で倍にもなった主食の価格を安定化、つまり下げることに政府が取り組まないというのは、実に奇妙なことです。「おこめ券」を配ったところで、コメ価格が下がるわけではありません。
円安を止めることこそ最大の物価高対策
物価高対策には、物価高で困る家計を支援する政策と、物価そのものを抑制する政策の2つがあります。政府の対策としては、即効性の観点から、まず、前者の家計支援が優先されるのでしょうが、家計支援には財政出動が伴うことから、いつまでも続けられるものではありません。
総合指数で3%前後という高いインフレを、目標の2%に落ち着けるためには、インフレを一定、抑制する政策が必要なはずです。とりわけ食料品やエネルギーの価格高騰が激しいのですから、1ドル=150円などと異常な円安を是正すること、少なくとも、これ以上の円安を止めることこそ、最大の物価高対策なのではないでしょうか。
147円前後だった円相場が、高市政権発足後に155円台まで円安が進んでいることは、要注意です。高市総理が日銀の利上げをけん制するような発言を繰り返していることが、その背景にあります。金融政策への考え方は色々あるにしても、結果的に、投機筋が安心して円を売れる環境を作っていることは、物価高対策に逆行していると言わざるを得ません。
「デフレ脱却」を強調する高市総理
もうひとつ心配な点は、高市総理の発言が、インフレに「寛容」と受け取られかねないことです。
高市総理は、「デフレを脱却したとは、まだ言えない」と述べた上で、「コスト上昇による物価上昇を需要が引っ張る物価上昇に変えていかなければならない」「そこまでは気が抜けない」と説明しています。
私には、ディマンド・プル型の物価上昇を実現するためには、物価上昇圧力はやや高めの方が良いと考えているように聞こえます。新内閣のプレーンに、「リフレ派」と称される人々が名を連ねるようになったことも、そうした見方に拍車をかけています。
経済政策の司令塔である経済財政諮問会議の民間議員に、日銀元副総裁の若田部昌澄氏らが任命された他、高市総理肝いりの日本成長戦略会議にも元日銀審議委員の片岡剛士氏らが入りました。
問題は、どこまでインフレを許容するのか
そもそも今のインフレが、「コスト・プッシュ(上昇)」か、はたまた「ディマンド・プル」なのか、というのは、概念的には理解できても、消費者が実際に買い物をする際に意識するものではありません。経済学の研究としては意味があっても、現実の経済活動で定量的にそれを把握することは困難です。国民にとっては、3%ものインフレは、コスト・プッシュであろうが、ディマンド・プルであろうが、それでは生活が苦しい、ということに尽きています。
インフレに寛容な思考や政策がとられるのであれば、国民生活の実情や選挙での「民意」とは、ズレが生じていくことになるでしょう。何より、2025年の日本は、アベノミクスが始まった2012年とは全く環境が異なっているのです。
インフレ加速で一番困るのは、賃金がなかなか上がらない一般の家計であり、実質的に資産が目減りする高齢世帯です。逆に一番得をするのは、「借金」を抱えているセクター、その代表は「日本政府」です。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)
・「インフルにかかる人・かからない人の違いは?」「医師はどう予防?」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】
・「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】
・【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【後編】「どちらからホテルに誘うことが多かった?」記者と小川晶市長の一問一答(9月24日夜)

