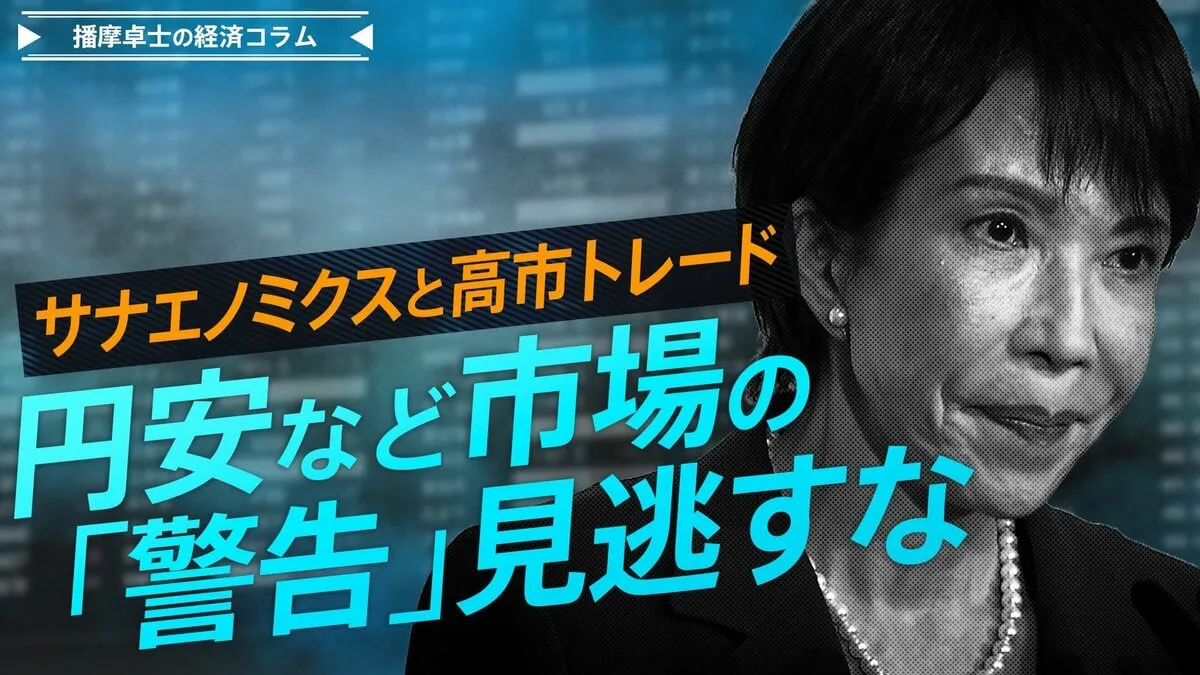
自民党で高市総裁が誕生したことを受けて、金融市場では、株高、円安という「高市トレード」が進行しました。積極財政と金融緩和を軸とする高市新総裁の経済政策「サナエノミクス」は、インフレ時代において、現実的な対応を迫られることになるでしょう。
【写真で見る】サナエノミクスと高市トレード、円安など市場の「警告」見逃すな
日経平均は4万8000円台に
大方の予想を覆し、高市早苗氏が当選した自民党総裁選挙を受けて、金融市場は、反射神経的に株高、円安で反応しました。日経平均株価は、週明け6日には、2175円、率にして4.75%も急騰しました。積極財政が持論の高市氏の総裁就任で政策期待が一気に高まり、具体的には、防衛関連銘柄や、半導体やAIといった経済安全保障関連銘柄が大きく買われました。その後9日にも、845円高を記録し、4万8000円台後半まで値を上げました。4万円の大台回復が7月だったことを思うと、日経平均は3か月で2割上昇したことになります。
もっともこの間は、アメリカの株価が、FRBの利下げ期待を背景に、ハイテク株を中心に最高値を更新しており、日本の株高のどこまで「高市効果」と言えるのかは、難しいところです。
円安進行、一時1ドル153円台に
一方、為替市場では急速に円安が進みました。高市氏が元来、金融緩和論者で、日銀の描く利上げが遠のいたと受け止められたことや、拡張的な財政政策による国債増発と財政赤字拡大が連想されたためです。総裁選挙前に1ドル147円台だった円相場は、一時153円台へと、総裁選前から6円もの急速な円安が進みました。
高市氏の経済政策の実像は
アベノミクスの継承者を自認する高市氏は、自らの信条を、総裁選挙や当選後の記者会見で、はっきりと表明しました。経済に果たす政府の役割を重視して「責任ある積極財政」を唱え、場合によっては赤字国債発行もやむなしという姿勢です。
金融政策についても、「責任を持つのは政府であり、日銀には金融政策の手段が任されている」と明言、日銀が政府の方針に従うのは当然という言いぶりでした。当然のことながら、金融市場は、日銀の利上げをけん制した発言と受け止めました。
ただ、高市氏は積極財政について、「責任ある」という言葉を加えることは忘れていませんし、利上げについても今回は、前回の総裁選の時のように「今、利上げをするのはアホやと思う」といった直接的な表現は避けています。
消費税減税は掲げず
今後、高市政権ができた際に、具体的にどんな経済政策を打ち出していくのかは、連立や協力のパートナーがどうなるかによっても、随分変わってくると思いますが、高市氏の総裁選挙での公約を見る限り、他の候補者と、それほど大きな違いがあるわけではありません。
かつて高市氏は、食料品への消費税減税を主張していましたが、「これまで自らの主張が党内で多数の支持を得られなかった」として、事実上、これを取り下げました。当選後も、前向きな発言はしていません。
ガソリン税の暫定税率廃止や、いわゆる年収の壁の引き上げは、去年暮れに、自民、公明、国民民主の3党が最終目標として幹事長レベルで合意していたこともあり、総裁選の他の候補者も言及していたことです。その意味では、高市政権で驚くような経済政策が出てくるとみる向きは、今のところありません。
強いて言えば、ガソリン税暫定税率に関し、高市氏は、軽油(ディーゼル燃料)についても廃止を主張しており、2つあわせると必要な財源が年1兆5千億円に拡大するほか、軽油については地方税であることから、その手当の議論が複雑になるという点が挙げられるでしょう。
アベノミクスと全く違う環境
信条的には「アベノミクス信奉」でも、驚くような政策が予感されないのは、2012年のアベノミクス開始時と、2025年の今の経済状況が、違い過ぎるからです。2012年12月は、消費者物価はマイナス0.1%で、1ドル86円台、長期金利は0.8%、日経平均株価は1万円ちょっとでした。デフレで円高の時代ですから、為替を円安に導いてインフレを誘発することが適していましたし、金融緩和の手段として、日銀が国債を買い入れる余地が、まだありました。
2025年の今、物価は3%前後のインフレで、為替は1ドル150円台という円安水準で、長期金利は1.7%前後です。同じことをやったら、大変なことになってしまうでしょう。
最優先課題は物価高対策
当選後に高市氏は、最優先課題は物価高対策だと明言しました。食料品やエネルギーを中心とする今の物価高の、最大の要因は円安です。これ以上の円安の進行が、物価高対策を最優先に掲げる高市政権にとって好ましくないことは明らかです。逆に言えば、円安を止めることこそ、最も効果的な物価高対策と言えるでしょう。
仮に、一段の円安を受けて、日銀が利上げに踏み切る局面が来た際に、それを無理やり止めて、さらに円安に向かわせるほど、高市氏は「アホやない」と、私は思います。
実は、高市氏のロジックと日銀のロジックは、奇妙なほど同じです。高市氏は「物価は表面上2%を超えているが、需要が引っ張るような2%の物価上昇には至っていない」と述べました。これは植田総裁が繰り返し述べている、「基調的な物価上昇はまだ2%に至っていない」という認識と同じです。その意味では、緩和的金融環境を維持しながら、政策を微調整していくという文脈で、一定の落としどころは、見いだせるのではないでしょうか。
何よりも怖い「日本国債売り」
実際、アベノミクスと異次元緩和の結果、日本の財政・金融政策の選択肢は、大きく制限されています。誰が総理大臣であろうと、最も警戒しなければならないことは、日本国債売り、つまり市場金利が急騰することです。借金である財政赤字を膨大に抱える日本にとって、金利の急騰は、利払い費の増大に直結します。その分、使える予算が圧迫されてしまうのです。
イギリスのトラスショックを持ち出すまでもなく、こうした市場心理の急変は、いったん起きてしまうと、沈静化に時間がかかり、厄介です。
10年物国債の利回りである日本の長期金利は、10日、一時1.7%を記録し、17年ぶりの高い水準を更新しています。インフレ定着時代には、長期金利の一定の上昇が避けられないだけに、一層の注意が必要な状況です。
市場の警告を見逃さないバランスを
8日付のイギリスのフィナンシャル・タイムズ紙は、高市氏に対し、「アベノミクスを継承するな」とした上で、財政支援は「最も苦境にある層と最も生産的な分野に限るべきだ」と主張しました。また、ワシントンにある有力シンクタンク、ピーターソン国際研究所所長で、知日派でもあるアダム・ポーセン氏も、「積極的な財政政策は市場の動揺を招く恐れがある」と懸念を示しています。
各国の財政赤字が拡大し、どの国でも、長めの金利が大きく上昇する中で、国際的に、債券市場動揺への警戒感が、かつてないほど高まっています。
自分の言葉で明解に語る高市新総裁の発言は、魅力的な分、市場へのインパクトも大きくなります。為替や金利など、金融市場から発せられる警告を見逃さずに、現実的に政策を進めるバランス感覚も、また持ち合わせていることを強く期待します。「日本がまた戻ってきた」と言われるためには、マーケットの「信頼」が欠かせないからです。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)
・【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから?」記者と小川晶市長の一問一答(9月24日夜)
・見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証”
・「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏(28)】

